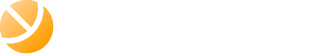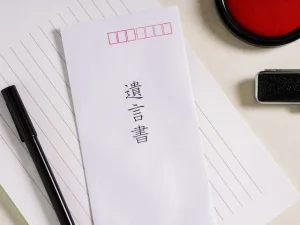「遺言書の作成は弁護士に頼むべき?」
「弁護士に遺言書の作成を頼むと費用はどのくらい?」
そろそろ遺言書を作成しようという段階で、弁護士に頼めば安心とは思いつつも、自分でできるのではないかと悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
しかし不備がある遺言書は無効になる場合や、遺言書の内容を正確に実行できないことがあります。特に不動産相続については、望まない共有状態を生んだり、不動産の売却ができなくなったりする可能性も。
自分の財産を希望通り相続人に遺すためには、遺言書作成を弁護士に依頼するのが得策でしょう。
今回は、遺言書の作成にまつわる注意点や弁護士に依頼すべきメリットなどについて解説します。
不動産相続の流れ

不動産相続は、基本的に以下の流れで進めます。
- 遺言書の有無や内容の確認
- 相続人や相続財産の調査
- 不動産の遺産分割協議
- 不動産の名義変更手続
- 相続税の申告と納付
不動産相続の手続は全体の流れをしっかりと理解し、着実に進めることが大切です。
遺言書の有無や内容を確認
不動産相続では、まず遺言書の有無とその内容について確認する必要があります。
遺言書が存在する場合、被相続人の遺志である遺言書の内容に従って、各種相続手続を進めるのが一般的です。
遺言書には自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類がありますが、ほとんどの場合で自筆証書遺言か公正証書遺言の方式がとられます。それぞれのメリット・デメリットは以下のとおりです。
| メリット | デメリット | |
| 自筆証書遺言 | ・遺言者が手書きするため手軽に作成できる
・遺言執行の際に裁判所の検認が必要 |
・書き方や内容に間違いがあると無効になる
・紛失や隠匿・改ざんのおそれがある |
| 公正証書遺言 | ・公証人が関与するため形式不備で無効になる心配がない
・公証役場が遺言書を保管してくれる |
・自筆証書遺言に比べ、手間や費用がかかる
・2人以上の証人を準備する必要がある |
自筆証書遺言の場合は法的に有効な遺言書を作成するため、弁護士などにチェックを受けての作成をおすすめします。
相続人や相続財産の調査
被相続人の遺産を分配するためには、法定相続人を特定し、被相続人が所有していた全ての財産を把握しなければいけません。
法定相続人とは被相続人の財産を相続できる親族で、民法にその範囲が定められており、確認のためには被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得します。戸籍の見方にもコツが必要で、相続人に取りこぼしがあると遺産分割をやり直すことにもなるため、この時点から弁護士に相談しておくと安心でしょう。
相続財産の総額を算出するには、不動産以外の財産も含めた遺産総額を算出したうえで計算しなければいけないので注意が必要です。
多額の借金や滞納している税金など債務が発覚した場合には、相続放棄によって相続をしない選択もできます。
不動産の遺産分割協議
相続人と相続財産の確定後、遺産分割協議によって遺産の分割をおこないます。
不動産の遺産分割方法は、以下の4つです。
| 現物分割 | 現物をそのまま分ける |
| 代償分割 | 遺産を多く受け取った人が、他の相続人に代償金を支払って調整する |
| 換価分割 | 遺産を売却し、得た現金を分ける |
| 共有分割 | 遺産の持分を決め、共有名義とする |
遺産分割協議では相続人全員の合意を得る必要があり、話し合いがまとまらない場合は、不動産名義変更や銀行口座の名義変更などの相続手続を進められません。
不動産の名義変更手続
不動産の名義変更の手続には、以下の書類を準備する必要があります。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
- 相続人全員の戸籍謄本及び住民票
- 遺産分割協議書または分割内容の記載された遺言書
- 相続人全員の印鑑証明書
- 相続人関係図
- 固定資産評価証明書(最新年度のもの)
また、2024年4月1日より相続登記が義務化されるため、不動産の名義変更を怠った場合は過料を科される可能性があります。
(参照元:法務省「相続登記の申請義務化(令和6年4月開始)について」)
個人で書類を揃えるには手間と時間がかかることもあり、弁護士などの専門家に依頼するのが確実でしょう。
相続税の申告と納付
相続税が発生する不動産相続では、被相続人が亡くなったことを知った日(通常の場合は被相続人の死亡の日)の翌日から10か月以内に申告と納税をする必要があります。相続した財産が基礎控除額以下であれば相続税の申告は不要です。
(参照元:国税庁「相続税の申告と納税」)
相続税の納付義務は財産を相続したそれぞれの相続人が負担するため、相続人が複数いる場合には相続人ごとに納付書を作成し納付しなければなりません。相続税は原則として、金銭による一括納付です。
相続税の納付方法には、以下のような方法があります。
- 銀行など金融機関での納付
- コンビニでの納付
- クレジットカードでの納付
- 税務署の窓口での直接納付
期限までに申告や納付をしなかった場合は、延滞税などのペナルティが発生するため注意しましょう。
遺言書作成を弁護士に依頼するメリット

遺言書の形式や内容に不備があり、遺言書を執行できない事態は少なくありません。弁護士に遺言書の作成を依頼することで、次のようなメリットが得られます。
- 正しい遺言書を作成できる
- 遺言書に記載する内容を相談できる
- 相続財産を正確に調査できる
- 相続トラブルを事前に予防できる
- トラブルが起きた場合も解決がスムーズ
- 遺言執行者を依頼できる
それぞれについて解説します。
正しい遺言書を作成できる
遺言書には厳格な要式があり、自筆証書遺言を自分で作成すると、不備により遺言書が無効になるリスクが高まります。遺言書が無効になってしまっては意味がなく、相続人にも手間や迷惑をかけることになるため、弁護士に有効な遺言書の作成を依頼するのが確実です。弁護士は法律の専門家のため、法律の観点から正しい遺言書を作成できます。
遺言書に記載する内容を相談できる
遺言書の内容そのものに悩んでいるときに、どうするべきかアドバイスを求められるのも弁護士です。法律の専門家である弁護士に対し、被相続人が実現したい遺言内容を、どのように記載すれば有効になるか相談できます。
また被相続人がどのような相続を望むのかを弁護士に伝えれば、弁護士はそれを文字にして間違いのない遺言書を作成してくれます。
相続財産を正確に調査できる
弁護士は職権によりさまざまな書類を取り寄せられるため、個人でおこなうよりもスムーズかつ正確に、遺言書に記載する相続財産を調査・記載できます。
被相続人が亡くなった際は遺言書の内容に沿って遺産を分割することになるため、財産の分け方を正しく指定し、相続財産の全容を正しく把握・記載することが重要です。相続財産の記載漏れなどがあると、遺言者の希望通りに財産の分割ができません。
また、分割しづらい土地や家といった不動産について、どのように対処すれば良いのかなど、弁護士にアドバイスを求められます。
相続トラブルを事前に予防できる
早い段階から弁護士に依頼しておくことで、遺言者の死後に発生しがちな相続トラブルについて事前の対策が可能です。
相続財産に不動産が含まれていると、分割方法などで相続人同士がもめてしまうことが多々あります。弁護士はそれらに関する過去の判例についての知識があるため、遺言書の内容に対し他の相続人がどのような感情を持ち、法的にどのような主張をしてくるか、あらかじめ想定できます。
そのため、弁護士は法律的観点から発生しうる相続問題を予測し、遺言書作成の段階で適切な解決策や対処法を提案できるのです。
大切な財産を遺したいと考えている遺言者は、自分の死後に問題を生まないためにも、弁護士の協力を得て事前にしっかりと対策を講じておきましょう。
トラブルが起きた場合も解決がスムーズ
どれだけ事前に相続トラブルを予防しても、相続人の感情のもつれなどが原因でトラブルを回避できない場合があり、当事者だけの話し合いでは解決策が見いだせないこともあります。
そんな場合でも、弁護士の関与により問題をスムーズに解決し、親族同士で何年も争い続けなければいけない事態を避けられます。
遺言執行者を依頼できる
遺言内容を確実に実現するためには、弁護士に「遺言執行者」を依頼するのがおすすめです。遺言執行者には親族を指定するケースが多いですが、弁護士などの専門家を指定することも可能です。
遺言執行者は、遺言者の死後に遺言書の内容を実現するために行動する人のことです。遺言内容の実現は、遺言の内容や遺産の種類等によっては、かなりの手間がかかります。弁護士に遺言執行者を任せることにより、遺言の内容をスムーズかつ確実に執行できます。
遺言執行者がおこなう手続には、以下のようなものがあります。
- 相続人に遺言の内容を通知する
- 相続人調査と相続財産の調査を行う
- 相続財産の目録を作成し、相続人に交付する
- 遺言の内容を実現するために手続を行う(子の認知・相続登記・預金の解約や分配など)
- 遺言執行の業務報告・完了の報告
相続人の中から遺言執行人を指定すると、その相続人は知識がないまま手続を進めることになり、手間や時間もかかり重いストレスをかけることになります。
大切な家族に負担を与えないためにも、遺言執行者を弁護士に指定するのが適任です。
遺言書作成の注意点

民法では遺言について下記のように定められており、法律に定めるとおりに作成しなければ遺言書は無効になります。
| (遺言の方式)
第九百六十条 遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。 |
遺言書が無効になる例を含め、他にも遺言書作成の際に注意すべき点には以下のようなものがあります。
- 形式不備などで無効になる可能性がある
- 裁判所での検認が必要
- 遺言書で指定できること・できないこと
正しい遺言書を作成するため、以下に解説する注意点をしっかり認識しておきましょう。
形式不備などで無効になる可能性がある
作成した遺言書が無効になる例として、以下が挙げられます。
- 自筆証書遺言の押印がない
- 日付が明確でない(◯年◯月吉日など)
- 自筆証書遺言の「本文」をパソコンで作成している
これらはすべて、民法に定められた内容に準じています。
| (自筆証書遺言)
第九百六十八条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。 3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。 |
遺言書の全文・遺言の作成日付や遺言者氏名は、必ず遺言者本人が自書し押印しなければいけません。遺言の作成日付は、日付が特定できるよう正確に記載します。
自筆証書遺言は、以前は全文を本人が手書きする必要がありました。平成31年1月13日から「財産目録」にあたる部分はパソコンでの作成が認められ、預金通帳などのコピー添付も認められるようになりました。遺言者の手間を軽減するためです。
ただしこの場合には、財産目録の全てのページ(両面に記載の場合は両面とも)に署名・押印が必要です。
また自筆証書遺言は自ら手書きで作成することが定められているため、認知症などで意思表示が十分にできない人が作成したものは無効になる可能性があります。代筆されたものや音声が録音されたものは、自筆証書遺言として認められません。
自筆証書遺言書保管制度で守るべき要件
令和2年7月10日から、自筆証書遺言を法務局で保管してもらえる「自筆証書遺言保管制度」が始まりました。適切な保管によって遺言書の紛失や盗難・偽造や改ざんを防ぎ、相続人に発見してもらいやすくなる利点があり、広まりつつある制度です。
(参照元:法務局「自筆証書遺言保管制度」)
しかしこの制度を利用するには、民法に定められた要件の他に、守らなければいけないルールが細かく決まっています。主に書式についての規定ですが、受け付け時に法務局職員によってチェックされ、守られていなければ受け付けてもらえません。
(参照元:法務局「自筆証書遺言書保管制度 遺言書の様式等についての注意事項」、e-Gov法令検索 / 法務局における遺言書の保管等に関する省令附則)
非常に細かい要件を個人できっちり満たすのは難しいため、弁護士にアドバイスをもらったり、こまめに法務局に相談したりするといいでしょう。
要件さえ守って利用すれば、とても便利で安心な制度です。
裁判所での検認が必要
「検認」とは、遺言書の状態・加除や訂正の状態・日付・署名など遺言書の内容を明確にし、遺言書の偽造や改ざんを防止するための手続です。遺言書の有効・無効を判断する手続ではありません。
自筆証書遺言の執行のために検認手続は必須であり、遺言者の死後、家庭裁判所に申し立てて実施してもらいます。
公正証書遺言については、作成に公証人が関与しているため、検認手続は不要です。同じく、自筆証書遺言保管制度を利用して法務局で保管していた遺言書についても、検認の必要はありません。遺言書の保管を法務局に申請する際、法務局の窓口で職員から遺言書の形式やルールが守られているかチェックを受けることに加え、遺言書を法務局に保管してもらうことで偽造や改ざんが困難であると判断されるからです。
遺言書で指定できること・できないこと
遺言書に記載し、法的効力を持って指定できることは、主に以下のような事項です。
- 相続分・遺産分割方法の指定
- 遺贈
- 相続人の廃除・廃除の取り消し
- 生命保険金受取人の変更
- 特別受益の持ち戻しの免除
- 子の認知
- 未成年後見人の指定
- 遺言執行者の指定
- 祭祀承継者(仏壇などを守る人)の指定
反対に、遺言書に記載しても法的効力がなく、実行してもらえない事項には以下のような例が挙げられます。
- 遺留分侵害額の請求の禁止
- 子の認知以外の身分行為(結婚・離婚・養子縁組・離縁)
- 葬儀や埋葬の方法の指定(「散骨してほしい」など)
- 税金や公共料金の支払い者の指定
- オンラインデータ消去の依頼
遺言書で子の認知はできますが、養子縁組はできません。混同しないよう注意しましょう。
不動産相続を弁護士に依頼するメリット

専門的な知識がなければ解決が難しい不動産相続に関する問題やトラブルに対し、弁護士に依頼するメリットには次のような点があります。
- 不動産の価値を正確に把握できる
- 家賃収入のある不動産相続の相談ができる
- 相続したくない不動産への対処法を相談できる
- 他の相続人との交渉を任せられる
- 不動産以外の相続の手続を任せられる
相続人同士が争うことなく、スムーズに被相続人の不動産を相続するために、弁護士に依頼した場合のメリットについて理解しておきましょう。
不動産の価値を正確に把握できる
相続する不動産の価値は、弁護士に依頼すれば正確に算出してもらえます。不動産の価値の計算方法には、相続税路線価を用いる方法や、固定資産税・公示価格を用いる方法など複数あり、状況に応じて使い分ける必要があるため専門知識が必要です。
複数の相続人で公平に遺産を分割する際や相続税の納税の際にも、不動産の正確な価値を算出しておかなければいけません。
弁護士に依頼し、相続によって損をしないように不動産の価値を正確に把握しましょう。
家賃収入のある不動産相続の相談ができる
相続する不動産に家賃収入のある収益物件が含まれる場合は、物件の管理や賃貸借契約に関する問題もあり、一般的な不動産相続よりも手続が複雑になります。早い段階で弁護士に相談し、相続手続のアドバイスを受けることがおすすめです。
相続の開始から遺産分割協議が完了するまで、収益不動産は相続人全員の共有状態です。つまり賃料は各相続人が相続分に応じて受け取ることになり、管理や修繕にかかる費用も共同で負担することになります。
しかし、各相続人が毎月それぞれの相続分の割合で賃料を受け取るというのは現実的でなく、賃借人も面倒な賃料の支払いに応じてくれない可能性が高いです。
このような面倒な不動産相続も弁護士に依頼すれば、遺産分割協議から賃貸借契約の相続による引継ぎ・賃借人への通知といった必要手続を全て任せられ、スムーズに進めてもらえます。
相続したくない不動産への対処法を相談できる
相続人が相続を希望していない不動産に関しては、弁護士に依頼することで専門家の意見を踏まえた適切な処分方法を見つけられるでしょう。
相続したくない不動産の処分には、次のような方法があります。
- 売却する
- 自治体へ寄附する
- 国に引き取ってもらう
- 3ヵ月以内に相続放棄する
国に引き取ってもらう方法については、令和5年4月28日に施行された「相続土地国庫帰属制度」を利用します。この制度の利用については、審査の要件や負担金・手続について検討する必要があるため、弁護士への相談をおすすめします。
(参照元:法務省「相続土地国庫帰属制度について」)
他の相続人との交渉を任せられる
他の相続人との交渉を弁護士に任せることで、精神的な負担を減らせるのは大きなメリットです。不動産のように相続の分割が難しいケースでは、相続人同士が感情的になってしまい、協議がまとまらない場合も多々あります。
弁護士に依頼すると、相続人への連絡や交渉を任せられるため、相続人同士による争いを防げます。また法律知識を活かした適切なアドバイスを得られるため、相続人全員が納得できる解決方法を導き出せるでしょう。
不動産以外の相続の手続を任せられる
弁護士に依頼すれば、不動産以外の相続手続全般について一任できます。
遺産相続にはプラスの財産だけでなく、借金などの負債も含まれてくるため注意が必要であり、弁護士がついていれば安心です。
また、相続放棄や遺留分減殺請求など手続が複雑な事態になった場合も、弁護士に依頼していれば正確で迅速に手続を進められます。
相続手続を弁護士に依頼した場合の費用目安

相続に関する手続を弁護士に依頼した場合の、各費用の目安です。
あくまで目安であり、相続内容の複雑さや遺産総額の多さ、依頼する法律事務所によっても費用は変化します。
相談費用(目安:1万円)
法律事務所の初回相談料は、ほとんどの場合で30分5,000円、1時間1万円程度です。初回相談料無料の事務所もたくさんあるので、公式サイトを参考に探してみましょう。相談後に案件を依頼すれば相談料無料、というケースもあります。
遺言書作成費用(目安:10万~20万円)
遺言書の作成費用は10万円~20万円が相場ですが、遺言書の内容や相続財産の金額により、50万円を超えてくる場合もあります。相続人の関係や分割内容が複雑であるなど、遺言書の内容が特殊な場合は、弁護士費用も相場より高額になると考えておきましょう。
またこの遺言書作成費用の中には、公正証書作成時の公証人の手数料は含まれていません。
遺言書保管費用(目安:年間1万円)
作成した自筆証書遺言を自宅保管すると、紛失や偽造・改ざんのおそれがあります。弁護士に遺言書作成を依頼していれば、法律事務所で遺言書を保管してもらえます。
保管料の目安は年間1万円前後ですが、保管料として特別に費用を取らない事務所もあります。
なお、自筆証書遺言書保管制度を利用して法務局に遺言書を保管してもらう場合は、申請手数料も含めて3,900円です。
遺言執行にかかる費用(相続財産次第)
弁護士に遺言執行の依頼をした場合、不動産登記や預貯金の払い戻しなどをおこなう手数料として、30万円程度を目安に費用がかかります。遺産の総額や執行内容、事務所によっても金額は異なります。目安としては、最低報酬30万円~100万円にプラスして、相続による利益の0.5%から2%程度が報酬とされると考えておきましょう。
多くの事務所が費用計算の参考にしている「旧日本弁護士会報酬等基準」の内容は以下のとおりになっています。
| 相続財産の価額 | 遺言執行者の報酬 |
| 300万円以下 | 30万円 |
| 300万円〜3,000万円以下 | 24万円 +【相続による取得利益の2%】 |
| 3,000万円〜3億円 | 54万円 +【相続による取得利益の1%】 |
| 3億円を超える場合 | 204万円 +【相続による取得利益の0.5%】 |
(参照元:旧日本弁護士会報酬等基準)
旧日本弁護士会報酬等基準は平成16年3月に廃止されていますが、今も多くの法律事務所がこの基準を基に報酬を決めています。
その他の費用
その他費用には、交通費や実費・日当が該当します。不動産などの現地調査のために弁護士の出張が必要となる場合には、日当や交通費が必要です。
また公正証書遺言を作成する時には、遺言者と弁護士・証人が公証役場まで行くための費用、及び公証役場に支払う公証人の手数料が実費としてかかります。遺言者が動けない場合などに弁護士と公証人に自宅などへ来てもらう際にも、現地までの交通費や日当が必要です。
不動産相続を依頼する場合の弁護士の選び方

不動産相続を弁護士に依頼して円滑に進めるためには、適切な弁護士を選ぶ必要があります。
- 不動産相続の経験・実績や知識が豊富
- 他士業と連携している
- 対応がスムーズで説明がわかりやすい
- 複数の弁護士を比較検討する
弁護士を選ぶ際のこれらのポイントについて解説します、
不動産相続の経験・実績や知識が豊富
不動産相続の問題を解決するうえで、弁護士の経験と知識は重要な要素のひとつです。
弁護士にもそれぞれ得意分野があるため、全ての弁護士が不動産相続問題に詳しいとは限りません。
法律事務所の公式サイトをチェックし、相続案件をどれだけ扱っているのか確認してみましょう。事務所全体の案件の取り扱い件数だけでなく、弁護士個人のこれまでの経験年数や実績などの確認もおすすめします。
不動産相続に関する経験や知識が豊富な弁護士に依頼すれば、必要な手続をスムーズに進められるでしょう。
他士業と連携している
不動産相続案件の場合、弁護士を選ぶうえで他の士業と連携しているかどうかも重要な判断基準です。
不動産相続では、名義変更の相続登記のためには司法書士のサポートが必要であり、相続税の申告のためには税理士に相談する必要があります。司法書士や税理士と連携している法律事務所であれば、相続問題の全体を通して任せられるため、相続人である依頼者の負担を大幅に軽減できます。
対応がスムーズで説明がわかりやすい
いずれの案件を依頼する場合でも、弁護士の説明がわかりやすく対応がスムーズであることは欠かせないポイントですが、不動産相続の場合は特に重要な要素になります。
相続問題は複雑な手続と法律知識が必要になるため、依頼者が理解できるよう丁寧にわかりやすく説明してくれる弁護士を選ぶことで、状況を理解しながら安心して手続を任せられます。相続に詳しく経験や知識が優れた弁護士であっても、依頼者に対し横柄な態度をとるようでは信頼関係が築きにくく、満足のいく結果を得られない可能性も出てきます。
また、相続問題は時間が経つほど複雑化しやすく、相続税の申告期限もあるため、迅速に対応してくれる弁護士を選ぶ必要があります。依頼者の質問に対してすぐに回答してくれるか、メールや電話での対応は迅速か、案件に対する弁護士の姿勢をしっかりチェックしましょう。
複数の弁護士を比較検討する
法律事務所の公式サイトをチェックするだけでは、実態はなかなかわかりません。初回の無料相談を利用し、いくつかの法律事務所を訪ね、実際に弁護士と話をしてみましょう。事務所によって弁護士費用も違ってくるため、見積もりをもらって比べてみるのも重要です。
弁護士との面談の際には、不動産相続に関するわからないことを質問し、悩みや不安などを積極的に話しましょう。同じ質問や話をすることで、どの事務所が満足できる回答をしてくれるか、弁護士との相性なども比較しやすくなります。
不動産相続の遺言書作成は弁護士に依頼しよう

遺言書の作成を思い立ったら、早い段階で弁護士に相談し、遺言書作成の依頼をしましょう。弁護士のアドバイスを受けることで、自分の希望が正確に伝わらなかったり、不備により遺言が執行されなかったりするトラブルを回避できます。
特に面倒な手続も多い不動産相続については、相続人である大切な家族に負担をかけることなく希望どおりの相続を実現するために、遺言書の作成や執行などを弁護士にサポートしてもらいましょう。