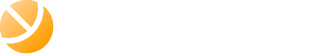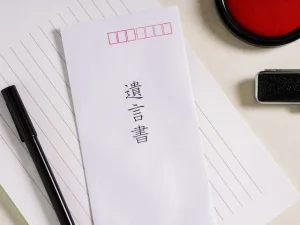日本では空き家問題が年々深刻化しており、総務省の「平成30年住宅・土地統計調査」によると、2018年の空き家数は846万戸、空き家率は13.6%でした。
将来的には野村総合研究所などの試算で、2033年には空き家が2,150万戸(全住宅の約3戸に1戸)に達するとの予測もありますが、これは対策が十分に講じられない場合の推計となっています。
特に問題視されているのが、相続によって発生する空き家です。実家を相続したものの活用されないまま放置される「相続空き家」は、防災・衛生・景観など様々な社会問題を引き起こしています。
本記事では、相続空き家の現状と対策、活用方法について詳しく解説します。
相続空き家の現状と問題点
増加する空き家と相続の関係
空き家の発生原因として、半数以上が相続によるものとされています。親が亡くなった後、実家の活用方法が決まらないまま放置されるケースが多く、2013年の調査では全国の空き家数は約820万戸にのぼり、全住宅の7戸に1戸が空き家という状況になっています。さらに、このまま対策が取られなければ、2033年頃には空き家数が2,150万戸に達し、全住宅の3戸に1戸が空き家になるという予測もあります。
空き家放置のリスク
空き家を放置することには様々なリスクがあります。適切に管理されず放置された空き家は損傷しやすくなり、台風で外装材や屋根材が飛散したり、地震により倒壊したりする危険性が高まります。また、ねずみや害虫が発生する、ごみの散乱や外壁の破損・汚れなど、衛生上や景観上の問題も引き起こします。
さらに、居住者がいないことで発生するトラブルもあります。雑草が茂っているなど一見して空き家とわかることで、放火、ごみの不法投棄、不法侵入や住み着きなどを助長することもあります。
これらの問題に対応するため、国は2015年に空き家対策特別措置法を全面施行し、特に問題が大きい空き家に対して行政代執行による取り壊し(除却)を可能とするなど対策を進めています。
相続空き家に関する法制度と税制
相続登記の義務化(2024年4月施行)
2024年4月から、不動産を相続した場合、その土地や家の名義変更(相続登記)が法律で義務化されました。これは、所有者が特定できない空き地や空き家が増加し、適切な対応ができず将来的にトラブルが発生するのを避けるために政府が決定した措置です。
相続登記の期限は、相続の開始および所有権を取得したと知った日から3年以内となっています。この期限を過ぎた場合、10万円以下の過料(行政制裁)が科される可能性があります(不動産登記法第164条の2)。また、住所変更登記も義務化され、不動産所有者の氏名や住所に変更がある場合は、2年以内に変更手続きを済ませないと5万円以下の過料が科される可能性があります。
空き家の譲渡所得3,000万円特別控除
空き家とその敷地を相続等で取得した場合、その空き家またはその敷地を売却する際、一定の条件を満たせば所得税・個人住民税において譲渡所得から3,000万円までが控除される特例措置を受けることができます。ただし、令和9年(2027年)12月31日までに売却することが必要です。
主な適用要件は以下の通りです。
- 相続開始の直前(老人ホーム等に入所の場合は入所の直前)まで被相続人が一人で居住していたこと
- 相続開始から譲渡の時まで、使用されていないこと
- 耐震基準を満たした家屋か、家屋の取壊しをした後の敷地を譲渡すること
- 昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された家屋であること
- 相続開始の日から3年を経過した年の12月31日までに譲渡すること
この特例は「被相続人居住用家屋等に係る譲渡所得の3,000万円特別控除」(租税特別措置法第35条の2の2)に基づく制度であり、譲渡前に第三者へ賃貸された場合は一度でも貸していれば要件を満たしません。
貸し出した場合は、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の要件から外れてしまうため、使うことができなくなります。
相続空き家の対処法

事前対策:親族間での話し合い
空き家の発生を防ぐためには、親などが元気なうちによく話し合い、方針を決めておくことが重要です。親が住まなくなった後の家をどうしたいのか、親の考えや思いを共有しておくことで、将来的な空き家の発生を防ぐことができます。
国土交通省も「空き家で困らないためには、自宅や実家の将来について家族と早くから話し合い、空き家になった場合は『仕舞う』(除却)、『活かす』(活用)の行動をとることが大切です」と呼びかけています。
相続空き家の活用方法
空き家を相続した場合、以下のような活用方法があります:
売却する
空き家に資産価値があり、賃貸や居住の予定がないならば、相続開始から3年以内に売却されるのがおすすめです。空き家の保有リスクを回避できますし、空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除を適用することができれば、税金を節税できる可能性があります。
売却するには相続登記が必要ですが、売却し現金化することで遺産分割がしやすくなる、維持費や管理の手間がかからなくなるなどのメリットがあります。
賃貸として活用する
空き家を賃貸用住居として貸し出すことも可能です。貸し出すことで家賃収入が見込めます。ただし、リフォームやクリーニング代などの初期費用、修繕費用、トラブル対応などが必要になります。また、年間20万以上の不動産所得がある場合には、確定申告が必要になります。
自身の居住用として使用する
自身の居住用不動産として、相続した住居を活用することもできます。相続した空き家の所在地によっては、売却や賃貸が難しい場合があります。しかし、自身の居住用建物、もしくはセカンドハウスとすれば、所有を続けながら、特定空き家の指定を回避して住宅用地の特例を適用させ続けることが可能です。
すでに持ち家があれば第2の拠点として利用するのも方法の一つです。生活のオンオフの切り替えができる、趣味を楽しむ場として利用できる、収納場所として利用できる、自然災害が多発する現代においてシェルターとしての役割を持つなど、多くのメリットがあります。
解体して土地のみ活用する
一度更地にしてから、売却やその他の活用方法を考える選択肢もあります。土地のみでの売却は、土地の上に古い家がある状態での売却よりも買い手がつきやすい場合があります。しかし、解体費用は高額になってしまう可能性が高く、一般的な木造住宅であっても100万円以上が相場であるため、コストがかかる点に注意が必要です。なお、他の要件を満たせば空き家控除が使えます。
空き家の管理方法
相続した空き家などの不動産で相続が発生した場合、その空き家を管理する責任は相続の権利がある法定相続人全員に管理責任が発生し得ます。適切な管理ができておらず、他の人に損害を与えてしまった場合(例えば、相続した実家の屋根が台風で飛んでしまい隣の家の窓ガラスを割ってしまった場合など)、その責任は相続人が負うことになります。
自分で管理するのが難しい場合は、以下のような選択肢があります:
空き家を手放したくないけれど、自分では管理ができない場合は、地域で活動するNPO法人などによる活用サービス(活用したい人とのマッチングや空き家の賃貸、管理など)を探すことも一つの方法です。市区町村によってはNPO法人や民間事業者と提携などを行い、サービスを紹介している場合もありますので、確認してみましょう。
相続放棄と空き家
空き家を相続したくないからという理由だけで、安易に相続放棄を選択するのはおすすめできません。相続放棄とは、被相続人の遺産を相続する権利や義務を一切放棄することで、相続放棄をするためには、原則として相続開始を知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に「相続放棄の申述」をしなくてはなりません。
相続放棄を選択すれば、空き家を相続することはありませんが、空き家以外のプラスの財産も相続できなくなりますし、必ずしも空き家の管理義務を免れるとは限りません。
相続放棄をした場合、法的には最初から相続人でなかったものとされます(民法939条)が、放棄が受理され、次の相続人が確定するまでの間に、空き家を事実上占有・管理していた場合は、その期間中の管理について民法940条等に基づく一定の責任を問われることがあります。
「空き家を相続したくないから」という理由だけで相続放棄を選択すると、空き家や被相続人のマイナスの財産(債務や未払金)だけでなく、空き家の他のプラスの財産(預貯金や他の不動産など)も引き継げなくなります。

また、相続放棄したことで、空き家について相続する者がいなくなり、空き家が国庫に帰属することになった場合、相続財産管理人が管理を開始するまでの期間などの管理義務が発生します。相続放棄が認められてすぐに、空き家の管理などについて何にもしなくていいようになるわけではない点に注意が必要です。
専門家への相談
空き家対策にあたっては、ご自身での対処が難しい時は、不動産、相続などの専門家に相談することも重要です。相続に関わる税金や法的手続きは複雑なため、税理士や司法書士など専門家のアドバイスを受けることで、最適な対策を取ることができます。
また、各地域では空き家相談会などのイベントも開催されています。これらを活用し、相続空き家について適切な対策を取っていくことが大切です。
まとめ
相続空き家問題は、日本社会における大きな課題となっています。空き家を放置すれば資産価値の低下だけでなく、防災・衛生・景観など様々な問題を引き起こす可能性があります。相続空き家を適切に管理・活用するためには、事前の親族間での話し合いが重要であり、相続後も売却、賃貸、自己使用など様々な選択肢を検討することが必要です。
2024年4月からの相続登記義務化により、今後ますます空き家の適切な管理・処分が求められる中、各種税制優遇措置を活用しながら、最適な対策を講じていくことが空き家所有者には求められています。専門家のアドバイスも得ながら、相続空き家と上手く付き合っていきましょう。
相続のご相談は尾畠・山室法律事務所へ