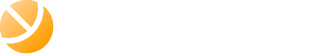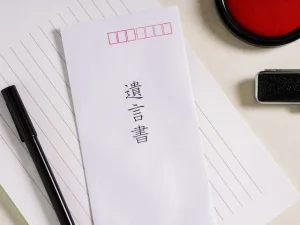近年、日本の高齢化社会において「家族信託」は認知症対策や資産管理の重要な選択肢として注目を集めています。高齢の親の財産管理が困難になるリスクに備え、家族や信頼できる人に財産管理を委ねる制度です。本記事では、家族信託の基本的な仕組みから、メリット・デメリット、導入方法まで、専門家の視点からわかりやすく解説します。
家族信託とは
家族信託は、資産を持つ方が特定の目的に従って、保有する不動産・預貯金等の資産を信頼できる家族に託し、その管理・処分を任せる仕組みです。いわば「家族の家族による家族のための信託(財産管理)」と言えます。
家族信託の3つの当事者
- 委託者:財産を託す人(例:高齢の親)
- 受託者:財産を管理する人(例:子や孫)
- 受益者:財産から利益を受ける人(例:委託者自身や家族)
この三者の関係により、信託契約が成立します。多くの場合、高齢の親(委託者)が子ども(受託者)に財産を託し、その利益を親自身(受益者)が受け取る形式で始まります。親が亡くなった後は、信託契約で定めた次の受益者(例:配偶者や子ども)に利益が移行します。
「家族信託」という用語は、一般社団法人家族信託普及協会によって商標登録されています。同協会では、「信頼できる家族に財産の管理処分を任せる信託」を「家族信託」と呼ぶことを普及させるために、商標登録をしています。
家族信託と民事信託の違い
民事信託とは、営利を目的としない私的な信託のことで、そのうち家族間で行われる財産管理目的の信託が「家族信託」と呼ばれることが多くあります。商事信託は金融機関など専門の受託者が営利目的で行う信託であるのに対し、家族信託は家族間の非営利目的の信託です。
家族信託が注目される背景
認知症による資産凍結問題
日本では高齢化に伴い認知症患者が増加しています。認知症になると判断能力が低下し、自分の財産を自分で管理できなくなります。この状態で不動産の売却や大きな契約行為を行おうとすると、成年後見制度を利用する必要があり、手続きが煩雑で制約も多くなります。
判断能力が失われると、自身で財産の管理・処分が困難になり、結果として事実上「資産が動かせない」状態になることがあり、これを俗に「資産凍結」と呼ぶことがあります。
家族信託を利用すれば、認知症発症後も受託者が委託者の意思に沿って柔軟に財産管理を行えるため、これを防ぐことができます。
成年後見制度の制約
成年後見制度には以下のような制約があります。
- 家庭裁判所の監督下におかれる
- 本人の財産を使った贈与や相続対策が基本的にできない
- 不動産の売却には裁判所の許可が必要
- 後見人の報酬が発生する
これに対し家族信託では、あらかじめ定めた信託契約に基づいて、より柔軟な財産管理が可能になります。
家族信託の主なメリット

1. 認知症対策としての機能
家族信託は、認知症などによって資金面や財産管理に困ることのないように、あらかじめ対策できる制度です。認知症になっても、受託者が委託者に代わって財産管理を行えるため、資産凍結のリスクを回避できます。信託契約で定めた範囲内であれば、不動産の売却や建て替え、賃貸契約の締結なども可能です。
補足情報
実際に処分や賃貸契約等を行うには、信託契約書に明確な目的・権限が記載されている必要があります。金融機関や登記官の実務的判断にも左右されるため、契約設計には注意が必要です。
2. 柔軟な財産管理が可能
家族信託では、信託契約書に記載した内容に従って財産管理を行います。成年後見制度では原則として本人の財産は本人のために使うという制約がありますが、家族信託では次世代への贈与や相続対策など、より幅広い目的で財産を活用できます。
具体的には:
- 暦年贈与の継続
- 相続税対策の実施
- 孫への教育資金の提供
- 不動産の有効活用
などが、委託者の判断能力が低下した後も継続して行えます。
3. 次世代への円滑な資産承継
家族信託では、委託者が亡くなった後の財産の承継先も指定できます。これにより、複雑な相続問題を未然に防ぎ、円滑な資産承継が可能になります。特に以下のようなケースで効果を発揮します:
- 複数の不動産を特定の相続人に承継させたい場合
- 事業用資産を事業継承者に確実に引き継がせたい場合
- 相続人の中に認知症の方や障がいのある方がいる場合
4. 不動産管理の効率化
賃貸アパートなど収益不動産を所有している場合、家族信託を活用することで管理業務を受託者に委託できます。入居者対応、修繕、賃貸契約の更新など、日常的な管理業務を受託者が行うことで、高齢の所有者の負担を軽減できます。
また、共有不動産の場合、一部の共有者が認知症になると処分が困難になりますが、家族信託を利用して管理権限を一人の受託者に集中させることで、この問題を解決できます。
5. 障がいのある子どもの将来対策
障がいのある子どもがいる場合、親亡き後の生活や財産管理が大きな懸念事項となります。家族信託を活用すれば、親の財産を子どものために管理・運用する仕組みを構築できます。また、信託財産から定期的に生活費を支給する仕組みを作ることも可能です。
生活保護受給者が相続で一定額以上の財産を取得すると、生活保護が打ち切られる可能性がありますが、家族信託を利用して適切に設計すれば、生活保護を維持しながら追加的な生活支援を行える可能性があります(ただし、個別のケースによって判断が異なるため、専門家の助言が必要です)。
家族信託の主なデメリット
1. 専門的な知識が必要
家族信託は比較的新しい制度であり、法律・税務面で複雑な側面があります。信託法、民法、相続法、税法など多岐にわたる知識が必要であり、専門家のサポートなしに適切な設計を行うことは困難です。
信託契約の作成や登記手続きなどには専門的な知識が必要であり、自分で手続きを行うことは現実的ではありません。また、専門家の中でも家族信託に精通している人は限られているため、適切な専門家を見つけることも重要です。
2. 身上監護ができない
家族信託では財産管理はできますが、委託者の身上監護(生活や療養に関する世話や介護施設への入所契約など)はできません。家族信託はあくまでも財産管理に特化した制度です。
例えば、以下のような行為は家族信託では対応できません。
- 医療契約の締結
- 介護施設への入退所手続き
- 介護サービスの契約
これらの行為には本人の同意が必要であり、認知症で判断能力が低下した場合は別途成年後見制度や任意後見制度の利用を検討する必要があります。
3. 信託できない財産がある
不動産、預貯金、有価証券など多くの財産は信託できますが、以下のような財産は信託が難しいか不可能です。
- 年金受給権:年金は本人にしか支給されないため信託できません
- 農地:農地法の制限により、農業委員会の許可が必要
- 生命保険の契約者の地位:保険会社の同意が必要
- 許認可が必要な事業用財産:許認可は本人に与えられるものであるため
- 借地権:地主の承諾が必要
これらの財産を含めた包括的な財産管理が必要な場合は、成年後見制度と併用するなどの対策が必要になります。
4. 受託者の負担が大きい
受託者は信託財産を適切に管理・運用する義務(善管注意義務)を負い、定期的な報告義務もあります。また、以下のような実務作業も発生します。
- 信託財産の管理・運用
- 信託口座の管理
- 受益者への定期的な収益の分配
- 信託に関する税務申告
- 不動産の場合は維持管理や入居者対応
特に家族が受託者を務める場合、これらの業務が負担になることがあります。受託者が高齢化した場合の対策(次の受託者の指定など)も必要です。
5. 法制度の変更リスク
家族信託は比較的新しい制度であり、法律の解釈や税務上の取り扱いが変更されるリスクがあります。実際に以下のような変更が過去にありました:
- 2022年:相続空き家特例が家族信託では使えなくなった(自宅の所有者が委託者でなくなるため)
- 2024年:信託終了時の登記手続きルールが変更された
このような制度変更により、当初想定していた効果が得られなくなる可能性があります。長期的な計画を立てる際はこのリスクも考慮する必要があります。

6. 費用がかかる
家族信託の設定には以下のような費用がかかります。
- 専門家への相談・設計料:20万円〜50万円程度
- 公正証書作成費用:5万円〜10万円程度
- 不動産の名義変更登記費用:1物件あたり数万円〜十数万円
- 信託口座の管理費用:金融機関によって異なる
また、信託期間中も税務申告や管理のための費用が継続的に発生します。これらの費用対効果を考慮して導入を検討する必要があります。
家族信託の適格性診断
以下のような方は家族信託の導入を検討する価値があります。
- 不動産や事業用資産など複数の資産を所有している
- 認知症発症後も柔軟な財産管理を望んでいる
- 相続対策や次世代への資産承継計画がある
- 障がいのある家族がいる
- 共有不動産の問題を解決したい
- 収益不動産の管理を家族に委ねたい
一方、以下のような方は家族信託よりも他の選択肢が適している可能性があります。
- 財産が預貯金のみで額が少ない
- 信頼できる家族がいない
- 身上監護が主な目的である
- 年金収入のみで生活している
- 認知症が進行している
家族信託の手続き方法
家族信託の一般的な手続きの流れは以下の通りです。
1. 専門家への相談と設計
まずは家族信託に詳しい専門家(弁護士、司法書士、税理士など)に相談します。家族構成、保有資産、将来の希望などをヒアリングし、最適な信託スキームを設計します。
この段階で重要なのは、家族全員での合意形成です。後々のトラブルを防ぐため、関係者が納得する形で進めることが大切です。
2. 信託契約書の作成
信託の目的、信託財産、受託者の権限、受益者の範囲、信託期間など、詳細な条件を定めた信託契約書を作成します。法的効力を高めるため、公正証書で作成することが一般的です。
信託契約書に含めるべき主な内容
- 当事者(委託者、受託者、受益者)の情報
- 信託の目的
- 信託財産の内容
- 受託者の権限と義務
- 受益者の権利
- 信託報酬(設定する場合)
- 信託の終了事由
- 後継受託者の指定
- 信託終了時の残余財産の帰属先
3. 信託専用口座の開設
信託財産を管理するための専用口座を開設します。この口座は「〇〇家族信託口」など、信託口座であることが分かる名義にします。これは受託者の善管注意義務の一環である「分別管理義務」を果たすために重要です。
信託専用口座の開設には金融機関によって手続きや必要書類が異なるため、事前に確認が必要です。一般的に必要な書類は
- 信託契約書(公正証書)
- 委託者・受託者の本人確認書類
- 印鑑証明書
- 銀行所定の申込書
ただし、実務上は対応できない金融機関も多いため、開設できる金融機関を事前に調査・相談などが必要です。
4. 信託財産の名義変更
不動産など名義がある財産については、受託者への名義変更手続きを行います。不動産の場合は「信託による所有権移転登記」を行います。
登記簿上の所有者は「〇〇信託受託者 △△」という形で表示されます。これにより、この不動産が信託財産であることが第三者にも明らかになります。
名義変更に必要な書類
- 信託契約書(公正証書)
- 委託者・受託者の印鑑証明書
- 不動産の登記識別情報
- 登記申請書
5. 信託の運営・管理
信託設定後は、受託者が信託契約に基づいて財産の管理・運用を行います。受託者は定期的に受益者に対して報告を行い、透明性を確保することが重要です。
また、毎年の確定申告も必要になります。信託財産から不動産所得などの収入がある場合は、通常の所得に加えて信託財産に関する明細書の提出が必要です。
家族信託が特に有効なケーススタディ
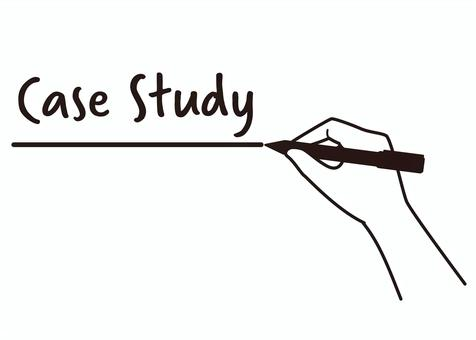
ケース1:認知症リスクがある高齢者の資産管理
状況:75歳の父親が複数の不動産を所有。軽度の物忘れが出始めており、将来の認知症に備えたい。
解決策:
- 父親を委託者・第一受益者、長男を受託者とする家族信託を設定
- 不動産の管理・処分権限を長男に託す
- 父親が認知症になった場合でも、長男が不動産の売却や建て替えなどを実行可能
- 父親死亡後は、信託契約で定めた次の受益者(例:母親)に収益が移行
ケース2:障がいのある子どもの将来サポート
状況:65歳の両親に知的障がいのある40歳の息子がいる。親亡き後の息子の生活を心配している。
解決策:
- 両親を共同委託者、信頼できる親族(例:妹)を受託者、障がいのある息子を受益者とする家族信託を設定
- 自宅と預貯金を信託財産として託す
- 両親死亡後も、受託者が息子のために財産を管理
- 信託財産から定期的に生活費を支給する仕組みを構築
- 障害年金と併用することで、安定した生活基盤を確保
ケース3:共有不動産の円滑な管理
状況:4人の兄弟姉妹が実家を共有相続。一人が遠方に住んでおり、また一人は高齢で判断能力の低下が心配。
解決策:
- 4人を共同委託者、長男を受託者とする家族信託を設定
- 実家の管理・処分権限を長男に集中
- いずれかの共有者が認知症になっても、不動産の管理・処分が可能
- 将来的な売却や活用方法についてあらかじめ信託契約書に記載
ケース4:事業承継と相続対策の両立
状況:70歳の経営者が会社株式と事業用不動産を所有。事業は長男が継いでいるが、相続時に次男・長女との間で争いになる可能性がある。
解決策:
- 経営者を委託者・第一受益者、長男を受託者とする家族信託を設定
- 事業用不動産と一部の株式を信託財産として託す
- 経営者の生存中は経営者自身が収益を受け取る
- 経営者死亡後は長男が第二受益者となり、事業継続に必要な財産を確保
- 次男・長女には他の財産で相続分を確保するよう遺言を準備
家族信託と併用すべき他の制度
家族信託だけでは対応できない部分を補完するため、以下の制度と併用することを検討します。
1. 任意後見制度
身上監護(医療や介護の契約など)に対応するため、家族信託と任意後見制度を併用するケースが増えています。財産管理は家族信託で、身上監護は任意後見人が担当するという役割分担です。
2. 遺言
家族信託では対応できない財産(年金受給権など)の承継や、信託終了後の財産分配について定めるために、遺言を併用することが効果的です。
また、年金受給権は相続することもできないため注意が必要です。
3. 生命保険
信託財産の管理運営資金の確保や、相続税の納税資金の確保のために、生命保険を活用するケースもあります。
4. 成年後見制度
家族信託で対応できない財産がある場合や、家族信託設定後に予期せぬ状況変化があった場合のセーフティネットとして、成年後見制度を併用することもあります。
家族信託の税務上の考慮点
家族信託には特有の税務上の考慮点があります。
1. 信託設定時の税金
信託設定時に贈与税や不動産取得税が課税されるケースがあります。委託者=受益者である「自益信託」の場合、通常は贈与税は課税されませんが、委託者以外の者が受益者となる「他益信託」の場合は贈与税の課税対象となることがあります。
2. 信託期間中の課税関係
信託財産から生じる所得は、原則として受益者に課税されます(受益者課税原則)。受託者は信託財産に関する確定申告書を作成・提出する必要があります。
3. 信託終了時の税金
信託終了時に残余財産が最終受益者に移転する際、信託終了時に残余財産が移転する時点での受益者が誰かによって、贈与税または相続税が課税されるかが異なります。たとえば、委託者の死亡を原因とする場合は相続税課税が原則です。
4. 特例措置の適用可否
相続税の小規模宅地等の特例や、空き家の譲渡所得特別控除など、各種特例措置の適用可否については、家族信託の場合に制限がある場合があります。
家族信託のリスク管理
1. 受託者の不正リスク
受託者に大きな権限が集中するため、不正行為のリスクがあります。これを防ぐための対策としては
- 信託監督人の選任
- 定期的な報告義務の設定
- 複数の受託者の選任
- 後継受託者の指定
特に受託者と受益者が異なる場合には、信託監督人を任命することで、受託者による不正の抑止や、受益者の利益の確保が期待できます。信託契約書で任命を定めることが重要です。
2. 受託者の高齢化・死亡リスク
長期間にわたる信託では、受託者自身が高齢化したり死亡したりするリスクがあります。信託契約書に後継受託者を指定しておくことが重要です。
3. 法改正・税制改正リスク
法律や税制の改正により、設計時に想定していた効果が得られなくなるリスクがあります。定期的に専門家に相談し、必要に応じて信託内容を見直すことをおすすめします。
4. 家族関係の変化リスク
離婚、再婚、相続人の増減など、家族関係が変化するリスクがあります。信託契約書にこれらの事態への対応方法をあらかじめ記載しておくことが重要です。
まとめ
家族信託は、認知症対策や財産管理、資産承継対策として非常に有効なツールです。しかし、メリットとデメリットを十分に理解し、自分の状況に合った設計を行うことが重要です。
理想的な家族信託を実現するためにも、家族信託をきっかけとしたトラブルを回避するためにも、利用を検討する場合は家族信託の経験と実績が豊富な専門家に相談しましょう。
家族信託に限らずですが、どのような制度にも必ず落とし穴があります。特に家族信託においては、法律・税務面で複雑な面もあり、十分な注意が必要です。家族信託をする際には、必ず専門家と相談しながら進めることをお勧めします。
家族信託は適切に設計・運用すれば、認知症対策や資産管理の強力なツールとなります。ご自身やご家族の状況に合わせて、メリット・デメリットを十分に検討した上で導入を検討されることをおすすめします。