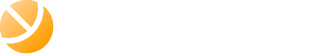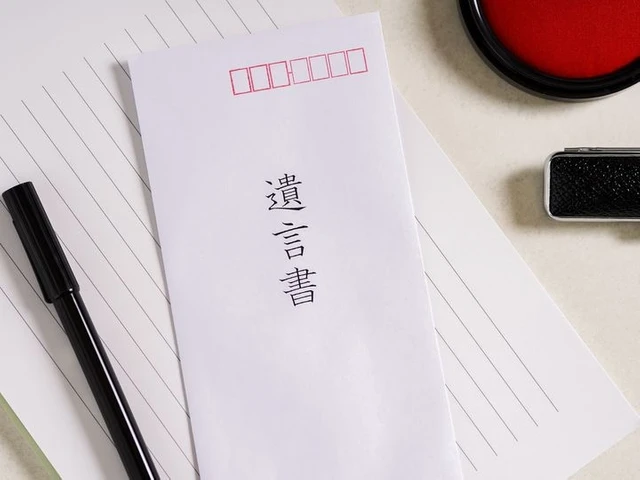「遺言書なんて、まだ早い」多くの方がそう考えています。しかし、遺言書がないために起こる相続トラブルは年々増加しており、家庭裁判所に持ち込まれる遺産分割事件は2022年には約12,000件にも上りました。遺言書は単なる財産分けの指示書ではありません。家族の絆を守り、あなたの想いを次世代に伝える大切なメッセージなのです。
特に2024年4月から相続登記が義務化され、2025年には遺言書保管制度の利用者が急増しています。法改正により遺言書作成の重要性はますます高まっており、正しい知識を持って準備することが必要になりました。遺言書があれば防げたはずの争いで、仲の良かった家族が絶縁状態になるケースも珍しくありません。
弁護士として数多くの相続案件に携わってきた経験から言えるのは、適切な遺言書があれば相続手続きは驚くほどスムーズに進むということです。一方で、形式不備により無効となってしまう遺言書や、かえってトラブルの種となる遺言書も少なくありません。
本記事では、遺言書作成における重要な7つのポイントと、実際の書き方について詳しく解説します。自筆証書遺言と公正証書遺言の違い、費用相場、必要書類まで、遺言書作成に必要な知識を網羅的にお伝えします。法的に有効で、家族が困らない遺言書を作成するための実践的なガイドとして、ぜひ最後までお読みください。
遺言書の基礎知識を正しく理解する
遺言書とは何か
遺言書は、自分の死後、財産をどのように分配するか、誰に何を相続させるかを明確に示す法的文書です。民法では「遺言」と表記され、満15歳以上であれば誰でも作成できます。認知症などで判断能力が低下する前に作成することが重要で、医師の診断書があっても判断能力に疑いがある状態で作成された遺言書は無効となる可能性があります。
遺言書は単に財産を分けるためだけのものではありません。子の認知、未成年後見人の指定、遺言執行者の指定など、財産以外の重要な事項も定めることができます。また、祭祀承継者の指定により、お墓や仏壇を誰が引き継ぐかも明確にできます。
法的効力と要件
遺言書が法的効力を持つためには、民法で定められた厳格な要件を満たす必要があります。要件を一つでも欠けば、遺言書全体が無効となってしまいます。例えば、自筆証書遺言では全文を自筆で書く必要があり、パソコンで作成したものは原則無効です。ただし、2019年の法改正により財産目録についてはパソコン作成が認められるようになりました。
日付の記載も必須要件の一つです。「令和7年9月吉日」のような記載では無効となります。必ず「令和7年9月23日」のように、年月日を明確に記載しなければなりません。署名押印も欠かせない要件で、認印でも構いませんが、実印を使用することで真正性が高まります。
遺言書でできること・できないこと
遺言書で法的に効力を持つ事項は、民法により限定されています。財産の処分に関する事項として、相続分の指定、遺産分割方法の指定、遺贈、信託の設定などが可能です。身分に関する事項では、認知、未成年後見人の指定、後見監督人の指定ができます。
一方、遺言書に記載しても法的効力を持たない事項もあります。例えば、婚姻や離婚、養子縁組などは遺言では実現できません。また、「兄弟仲良く暮らすこと」「母の面倒を見ること」といった道義的な内容は、付言事項として記載はできますが、法的な強制力はありません。
意外と知らない「遺産」とは?知っておくべき基礎知識から実践的な対処法まで完全解説でも詳しく解説していますが、遺産には様々な種類があり、遺言書で扱える財産と扱えない財産を正確に把握しておくことが大切です。
2025年の最新法改正情報
2025年現在、遺言書に関する制度は大きく変化しています。最も注目すべきは、自筆証書遺言書保管制度の拡充です。2020年7月から開始された法務局での遺言書保管制度は、保管件数が急増しており、2025年には累計20万件を超える見込みです。保管手数料は3,900円と手頃で、紛失や改ざんのリスクがなくなるメリットがあります。
デジタル化の進展も見逃せません。2025年からは遺言書の存在を通知する「遺言書情報証明書」の電子交付が可能となりました。相続人は法務局に出向かなくても、オンラインで遺言書の有無を確認できるようになっています。
遺言書の3つの種類とそれぞれの特徴
自筆証書遺言のメリット・デメリット
自筆証書遺言は、最も手軽に作成できる遺言書です。費用がほとんどかからず、いつでも自由に書き直すことができます。内容を誰にも知られずに作成できるため、プライバシーを重視する方に適しています。法務局の保管制度を利用すれば、検認手続きも不要になります。
しかし、デメリットも存在します。形式不備により無効となるリスクが高く、実際に裁判で争われた遺言書の約3割が無効と判断されています。また、自宅で保管する場合は紛失や改ざんのリスクがあります。相続人が遺言書の存在に気づかない可能性もあるため、保管場所を信頼できる人に伝えておく必要があります。
文字が書けない状態になると作成できないため、健康なうちに準備することが大切です。病気で手が震えるようになってから書いた遺言書は、筆跡鑑定で本人のものか疑われることもあります。
公正証書遺言のメリット・デメリット
公正証書遺言は、公証人が作成する最も確実な遺言書です。法律の専門家である公証人が関与するため、形式不備で無効となることはほぼありません。原本は公証役場で保管され、紛失や改ざんの心配もありません。検認手続きも不要で、相続開始後すぐに執行できます。
公証人と証人2名の前で内容を確認するため、遺言能力があったことの証明にもなります。字が書けない方や、病床にある方でも作成可能で、公証人が病院や自宅に出張することもできます。
デメリットは費用の高さです。財産額により手数料が変わりますが、財産が1億円の場合、公証人手数料だけで約10万円かかります。証人への謝礼や弁護士への相談料を含めると、20万円以上になることもあります。また、証人に内容を知られるため、完全な秘密保持は困難です。
秘密証書遺言のメリット・デメリット
秘密証書遺言は、内容を秘密にしたまま、遺言書の存在だけを公証役場で証明してもらう方式です。遺言書の内容は誰にも知られず、公証人や証人も内容を見ることはありません。パソコンで作成することも可能で、署名さえ自筆であれば有効です。
ただし、実際にはほとんど利用されていません。年間の作成件数は100件程度で、全遺言書の0.1%未満です。公正証書遺言と同様に公証人手数料(11,000円)がかかる上、内容のチェックを受けられないため形式不備のリスクが残ります。検認手続きも必要で、メリットが少ないのが実情です。
3種類の遺言書比較
| 比較項目 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 |
|---|---|---|---|
| 作成費用 | 0円〜3,900円(保管制度利用時) | 5万円〜20万円程度 | 11,000円+証人謝礼 |
| 作成の手軽さ | いつでも自由に作成可能 | 公証役場での手続き必要 | 公証役場での手続き必要 |
| 形式不備リスク | 高い(約3割が無効) | ほぼない | あり(内容チェックなし) |
| 秘密保持 | 完全に秘密にできる | 証人に知られる | 内容は秘密にできる |
| 検認手続き | 必要(保管制度利用時は不要) | 不要 | 必要 |
| 紛失・改ざんリスク | あり(保管制度利用で解消) | なし | あり |
| 作成可能な状態 | 自筆できることが必要 | 署名できれば可能 | 署名できれば可能 |
| 年間作成件数 | 約10万件 | 約11万件 | 約100件 |
弁護士が教える失敗しない7つのポイント

1. 遺留分に配慮した内容にする
遺留分とは、一定の法定相続人に保障された最低限の相続分です。配偶者と子は相続財産の2分の1、親のみが相続人の場合は3分の1が遺留分となります。遺言書で特定の相続人に全財産を相続させても、他の相続人から遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。
例えば、財産が1億円で相続人が配偶者と子2人の場合、遺留分の総額は5,000万円です。配偶者の遺留分は2,500万円、子はそれぞれ1,250万円となります。長男に全財産を相続させる遺言を書いても、配偶者と次男から合計3,750万円の請求を受ける可能性があるのです。
遺留分トラブルを避けるためには、各相続人の遺留分を計算し、最低限の財産を確保する内容にすることが大切です。どうしても遺留分を下回る配分にする場合は、付言事項でその理由を丁寧に説明し、理解を求めることが必要です。生命保険を活用して、遺留分相当額を別途用意する方法も有効でしょう。
2. 財産目録を正確に作成する
財産目録は遺言書の要となる重要な部分です。不動産は登記簿謄本の記載通りに正確に記載します。「自宅」「実家の土地」といった曖昧な表現では、どの不動産を指すのか特定できません。所在、地番、地積、建物の場合は家屋番号まで正確に記載する必要があります。
預貯金は金融機関名、支店名、口座種別、口座番号まで明記します。「○○銀行の預金すべて」という記載でも有効ですが、複数の支店に口座がある場合は見落とす可能性があります。証券会社の口座、暗号資産、電子マネーなども忘れずに記載しましょう。
2019年の法改正により、財産目録はパソコンで作成できるようになりました。不動産は登記事項証明書のコピー、預貯金は通帳のコピーを添付することも可能です。ただし、財産目録の各ページに署名押印が必要な点に注意が必要です。
3. 遺言執行者を指定する
遺言執行者は、遺言の内容を実現する責任者です。預貯金の解約、不動産の名義変更、株式の移転など、相続手続きを単独で行う権限を持ちます。遺言執行者がいない場合、相続人全員の協力が必要となり、手続きが煩雑になります。
遺言執行者には相続人を指定することもできますが、他の相続人との利害対立が生じやすくなります。中立的な立場で手続きを進めるため、弁護士や司法書士などの専門家を指定することをお勧めします。専門家であれば、相続税申告や不動産登記など、複雑な手続きもスムーズに進められます。
遺言執行者の報酬も遺言書で定めておきましょう。「相続財産の3%」というように、財産額に応じた割合で定めるのが一般的です。報酬を定めていない場合は、家庭裁判所に報酬付与の申立てをする必要があります。
4. 付言事項を活用する
付言事項は法的効力を持ちませんが、遺言者の想いを伝える重要な部分です。なぜそのような分配にしたのか、家族への感謝の気持ち、将来への願いなどを記載できます。相続人の理解と納得を得るために、付言事項は極めて有効です。
例えば、事業を継ぐ長男に多くの財産を相続させる場合、「会社を守り、従業員の生活を支えてほしい」という想いを伝えます。介護をしてくれた長女に多く相続させる場合は、「献身的な介護に感謝している」と記載します。家族への個別のメッセージを含めることで、遺言書が単なる財産分けの指示書ではなく、最後の手紙となります。
中小企業の事業承継と相続対策|成功する5つの戦略と具体的手法を解説でも触れていますが、事業承継が絡む場合は特に付言事項が重要になります。後継者への期待と、他の相続人への配慮を丁寧に説明することで、円満な承継を実現できます。
5. 定期的な見直しを行う
遺言書は一度作成したら終わりではありません。家族構成の変化、財産状況の変動、法改正などに応じて、定期的に見直すことが必要です。特に、新たに孫が生まれた、不動産を売却した、相続人が亡くなったなどの変化があれば、速やかに見直しましょう。
見直しの目安は3年から5年に一度です。古い遺言書と新しい遺言書で内容が矛盾する場合、新しい日付の遺言書が優先されます。ただし、一部だけを変更する場合は、変更箇所を明確にすることが大切です。「令和5年3月1日付遺言書の第3条を次のように変更する」といった記載方法を用います。
公正証書遺言を作成している場合でも、自筆証書遺言で一部を変更することは可能です。ただし、後の混乱を避けるため、公正証書遺言を作り直すか、公証役場で変更の手続きをすることをお勧めします。
6. 相続人の特定を明確にする
相続人を特定する際は、氏名だけでなく、続柄、生年月日、住所などを記載して、誰のことか明確にします。「長男○○」「妻○○」という記載が基本ですが、同姓同名の可能性がある場合は、生年月日まで記載することが確実です。
相続人以外の人に財産を遺す場合(遺贈)は、特に注意が必要です。「お世話になった○○さんに」では特定できません。フルネームに加えて、住所、職業、関係性なども記載しましょう。法人に遺贈する場合は、正式名称、所在地、代表者名を正確に記載します。
将来生まれる子や孫に財産を遺したい場合は、「遺言者の死亡時に妻○○が懐胎している子」「長男○○の子として将来生まれる者」といった表現を用います。ただし、あまりに不特定な記載は、後の紛争の原因となるため避けるべきです。
7. 専門家のチェックを受ける
遺言書の作成は、一生に一度か二度の重要な手続きです。インターネットや書籍で得た知識だけで作成すると、思わぬ落とし穴にはまる可能性があります。特に、財産が多い場合や家族関係が複雑な場合は、必ず専門家のチェックを受けましょう。
弁護士は遺言書の内容について法的なアドバイスができ、将来の紛争を予防する観点から最適な内容を提案できます。税理士は相続税の観点から、節税効果の高い遺言内容を助言できます。司法書士は不動産の記載方法や登記手続きに精通しています。
専門家への相談料は、初回相談が5,000円から1万円程度、遺言書作成支援は10万円から30万円程度が相場です。財産額や複雑さにより料金は変わりますが、将来のトラブルを防ぐための投資と考えれば、決して高額ではありません。
遺言書の書き方実例
自筆証書遺言の書き方実例
実際の自筆証書遺言の記載例を見ていきましょう。以下は基本的な構成に沿った実例です。
遺言書
遺言者山田太郎は、次のとおり遺言する。
第1条 遺言者は、遺言者の所有する下記の不動産を、妻山田花子(昭和35年4月1日生)に相続させる。
土地
所在 東京都世田谷区○○一丁目
地番 123番4
地目 宅地
地積 200.50平方メートル
建物
所在 東京都世田谷区○○一丁目123番地4
家屋番号 123番4
種類 居宅
構造 木造瓦葺2階建
床面積 1階80.25平方メートル、2階60.30平方メートル
第2条 遺言者は、遺言者名義の下記預貯金を、長男山田一郎(昭和60年5月15日生)に相続させる。
○○銀行○○支店 普通預金 口座番号1234567
○○信用金庫○○支店 定期預金 口座番号7654321
第3条 遺言者は、前2条に記載した財産を除く遺言者の有する一切の財産を、長女山田京子(昭和63年8月20日生)に相続させる。
第4条 遺言者は、祭祀承継者として長男山田一郎を指定する。
第5条 遺言者は、本遺言の遺言執行者として、下記の者を指定する。
東京都千代田区○○一丁目2番3号
弁護士 鈴木法律事務所 鈴木次郎
令和7年9月23日
東京都世田谷区○○一丁目123番4号
遺言者 山田太郎 印
遺言書 テンプレートのダウンロードはこちら
編集するには必ずファイル→コピーを作成を行ってください。
財産目録の作成例
財産目録は別紙として作成し、遺言書本文で引用する方法が実務的です。2019年の法改正により、パソコンで作成可能になりました。
別紙 財産目録
不動産
(1)自宅土地建物
(登記事項証明書添付のとおり)
(2)駐車場用地
所在:東京都世田谷区○○二丁目
地番:456番7
地積:50.00平方メートル
預貯金
(1)○○銀行○○支店 普通預金 口座番号1234567
(2)○○銀行△△支店 定期預金 口座番号2345678
(3)ゆうちょ銀行 通常貯金 記号12345 番号67890123
有価証券
(1)○○証券○○支店 特定口座 口座番号98765432
保有株式:○○株式会社 1,000株
△△株式会社 500株
(2)投資信託:○○ファンド 口数10,000口
その他の財産
(1)自動車:トヨタ○○ 品川○○○あ1234
(2)ゴルフ会員権:○○カントリークラブ 正会員
(3)生命保険:○○生命 証券番号ABC123456
令和7年9月23日
山田太郎 印
(注)財産目録の各ページに署名押印が必要
【別紙 財産目録】テンプレートのダウンロードはこちら
編集するには必ずファイル→コピーを作成を行ってください。
よくある間違いと修正例
遺言書作成でよく見られる間違いを具体例で確認しましょう。
間違い例1:日付の記載漏れ・不明確
×「令和7年9月吉日」
○「令和7年9月23日」
間違い例2:財産の特定が不明確
×「自宅を長男に相続させる」
○「遺言者の所有する東京都世田谷区○○一丁目123番4の土地及び同所同番地4の建物を長男山田一郎に相続させる」
間違い例3:署名押印の不備
×「父より」「山田」(下の名前なし)
○「山田太郎」(フルネーム)+印鑑
間違い例4:訂正方法の誤り
× 修正液で消して書き直し
○ 二重線で消して訂正印を押し、欄外に「第3行目2字削除2字加入」と記載して署名
間違い例5:パソコンで本文作成
× 本文をパソコンで作成し、署名のみ自筆
○ 本文はすべて自筆(財産目録のみパソコン可)
遺言書の必須記載事項チェックリスト
| チェック項目 | 確認内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 表題 | 「遺言書」と明記されているか | なくても有効だが、あった方が明確 |
| 遺言者の特定 | 氏名がフルネームで記載されているか | 住所も記載するとより確実 |
| 日付 | 年月日が明確に記載されているか | 西暦でも和暦でも可 |
| 財産の特定 | 不動産は登記簿通りか | 登記事項証明書で確認 |
| 相続人・受遺者の特定 | 氏名、続柄、生年月日が明確か | 同姓同名対策として生年月日も記載 |
| 相続させる文言 | 「相続させる」「遺贈する」の使い分け | 相続人には「相続させる」を使用 |
| 署名 | 遺言者本人の自筆署名があるか | 氏名はフルネームで |
| 押印 | 印鑑が押されているか | 実印が望ましいが認印でも可 |
| 用紙・筆記具 | 改変されにくい素材か | ボールペンか万年筆を使用 |
| 訂正 | 法定の方式で訂正されているか | 訂正印と字数の記載が必要 |
遺言書作成の手続きと費用

自筆証書遺言の作成手続き
自筆証書遺言の作成は、基本的には個人で完結できます。まず、財産の棚卸しから始めましょう。不動産は法務局で登記事項証明書を取得し、預貯金は各金融機関で残高証明書を取得します。有価証券は証券会社で取引残高報告書を確認し、生命保険は保険証券で内容を確認します。
次に、相続人と相続分を決定します。法定相続分を基準にしつつ、各相続人の生活状況や貢献度を考慮して配分を決めます。遺留分を侵害しないよう、慎重に計算することが大切です。
下書きを作成したら、信頼できる第三者に内容を確認してもらいましょう。法律の専門家でなくても、客観的な視点でチェックしてもらうことで、記載漏れや不明確な表現を発見できます。清書は、改ざんを防ぐためボールペンか万年筆を使用し、修正液は使わないようにします。
法務局の保管制度を利用する場合は、遺言書保管所(法務局)に予約を入れ、必要書類を持参して申請します。手数料3,900円で、遺言書の原本を預けることができます。
公正証書遺言の作成手続き
公正証書遺言の作成は、まず公証役場への相談から始まります。最寄りの公証役場に電話で予約を取り、初回相談に臨みます。財産目録の案、相続関係説明図、印鑑証明書などを持参すると、具体的な相談ができます。
公証人と打ち合わせを重ね、遺言内容を確定させます。複雑な内容の場合は、2〜3回の打ち合わせが必要になることもあります。内容が固まったら、公証人が遺言書の原案を作成し、遺言者が確認します。
作成当日は、証人2名と共に公証役場に出向きます。証人は、未成年者、推定相続人、受遺者などは務められません。知人に頼むか、公証役場で紹介してもらうことも可能です(手数料別途1万円程度)。公証人が遺言内容を読み上げ、遺言者と証人が署名押印して完成です。
病気などで公証役場に出向けない場合は、公証人に出張してもらうことも可能です。出張手数料は基本手数料の1.5倍、日当は1日2万円(4時間以内は1万円)、交通費実費がかかります。
必要書類一覧
遺言書作成に必要な書類は、遺言の種類により異なります。
自筆証書遺言(法務局保管制度利用)の場合:
本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)、住民票(本籍地記載)、遺言書(A4サイズ、余白あり)、手数料3,900円、申請書(法務局所定の様式)が必要です。
公正証書遺言の場合:
遺言者の印鑑証明書(3か月以内)、戸籍謄本、住民票、不動産の登記事項証明書、固定資産評価証明書、預貯金の残高がわかる書類(通帳コピー等)、有価証券の明細、相続人・受遺者の住民票、証人の本人確認書類が必要となります。
書類の取得には時間がかかるため、余裕を持って準備しましょう。特に、古い戸籍謄本の取得や、遠方の不動産の登記事項証明書の取得には、2週間程度かかることがあります。
遺言書作成の費用比較表
| 項目 | 自筆証書遺言(自宅保管) | 自筆証書遺言(法務局保管) | 公正証書遺言 |
|---|---|---|---|
| 基本手数料 | 0円 | 3,900円 | 財産額により変動 |
| 〜100万円 | – | – | 5,000円 |
| 〜200万円 | – | – | 7,000円 |
| 〜500万円 | – | – | 11,000円 |
| 〜1,000万円 | – | – | 17,000円 |
| 〜3,000万円 | – | – | 23,000円 |
| 〜5,000万円 | – | – | 29,000円 |
| 〜1億円 | – | – | 43,000円 |
| 証人手数料 | 不要 | 不要 | 1人1万円程度 |
| 出張費用 | – | – | 基本手数料の1.5倍+日当 |
| 謄本交付 | – | 1通1,400円 | 1通250円×枚数 |
| 専門家相談料 | 0〜10万円 | 0〜10万円 | 5〜30万円 |
| 検認手続き | 必要(収入印紙800円) | 不要 | 不要 |
※公正証書遺言の手数料は、財産を相続させる人数により加算される場合があります
※遺言で遺言執行者を指定する場合は、1万1,000円が加算されます
専門家への依頼方法
遺言書作成を専門家に依頼する場合、まず相談先を選ぶ必要があります。弁護士は紛争予防の観点から最適な内容を提案でき、司法書士は不動産が主な財産の場合に適しています。税理士は相続税対策を重視する場合に、行政書士は費用を抑えたい場合に選択されます。
初回相談では、財産の概要、家族構成、遺言作成の目的を伝えます。【2024年最新】相続手続きと贈与税改正完全ガイド 4ステップで分かる相続対策と節税戦略でも解説されているように、相続税対策も含めた総合的なアドバイスを受けることができます。
見積もりを取得し、サービス内容を比較検討します。単に遺言書の文案を作成するだけなのか、財産調査から相続税シミュレーション、定期的な見直しまでサポートしてくれるのか、サービス範囲を確認しましょう。
依頼を決めたら、委任契約を締結します。着手金が必要な場合と、完成後の一括払いの場合があります。作成過程では、何度か打ち合わせを行い、納得いくまで内容を詰めていきます。完成後も、定期的な見直しのサポートを受けられる事務所を選ぶと安心です。
まとめ
遺言書作成は、家族への最後の贈り物です。適切な遺言書があれば、相続手続きは格段にスムーズになり、家族の絆を守ることができます。本記事で解説した7つのポイントを押さえ、自分に合った方式を選んで、早めに準備を始めましょう。完璧を求めすぎず、まずは作成することが大切です。定期的な見直しを前提に、今できる最善の遺言書を作成してください。