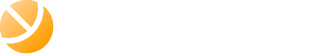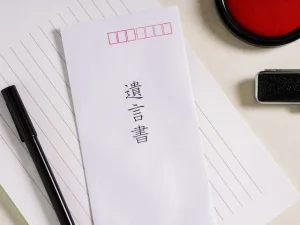ビットコインやイーサリアムをはじめとする暗号資産(仮想通貨)。数年前に投資した数万円が、気づけば数千万円、あるいは「億」を超える価値になっていた、という話も珍しくありません。
しかし、もしその暗号資産を保有したまま、持ち主が亡くなってしまったらどうなるでしょうか?
「親が仮想通貨を持っていたらしいが、IDもパスワードも分からない…」
「相続税を計算した時は1億円だったのに、納税する頃には3,000万円に大暴落していた…」
「バレないだろうと思って申告しなかったら、税務署から連絡が来た…」
暗号資産の相続は、従来の不動産や預貯金とは全く異なる、特有の危険性をはらんでいます。特に、その激しい価格変動(暴騰・暴落)は、相続税の計算と納税計画に深刻な影響を与えかねません。
本記事では、暗号資産の相続税評価という非常に複雑な問題について、国税庁が示すルールに基づいた正しい評価方法、価格変動リスクへの具体的な備え(生前対策)、そして最も怖い「申告漏れ」のリスクと対策を、相続と暗号資産の専門家である税理士の視点から、分かりやすく徹底的に解説します。
結論から申し上げると、暗号資産の相続は「事前の準備」と「専門知識」が不可欠です。この記事を読み、ご自身とご家族の大切な資産を守るため、今すぐできる対策を始めましょう。
第1章:なぜ今、暗号資産の「相続」が危険視されるのか?
ひと昔前まで「怪しい投資」と見られがちだった暗号資産も、今や多くの人が保有する一般的な資産の一つとなりつつあります。それに伴い、税理士のもとへも「暗号資産の相続」に関するご相談が急激に増えています。
なぜ、これほどまでに暗号資産の相続が危険視されるのでしょうか。それには、暗号資産が持つ特有の性質が関係しています。
1-1. 暗号資産保有者の増加と「億り人」の相続
暗号資産の市場は世界的に拡大を続けています。日本国内でも、口座開設数は年々増加傾向にあります。
特に問題となるのが、市場の黎明期(れいめいき)からビットコインなどを保有していた方々です。わずかな金額で手に入れた暗号資産が、100倍、1,000倍となり、気づけば数千万円、数億円の資産(いわゆる「億り人」)になっているケースです。
こうした方々が相続を迎える年代に差し掛かっており、相続財産の大部分が暗号資産、というケースも出始めています。預貯金や不動産が少なくても、暗号資産だけで相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を軽々と超えてしまうのです。
1-2. 相続を困難にする暗号資産の「3つの特異性」
暗号資産の相続が難しい理由は、大きく分けて3つあります。
① デジタル資産としてのアクセス問題
暗号資産は、紙の証券や通帳のような「モノ」が存在しません。すべてデジタルデータです。アクセスするには、取引所のIDやパスワード、二段階認証(スマホの認証アプリなど)、さらに個人ウォレットの場合は「秘密鍵(ひみつかぎ)」や「リカバリーフレーズ(復元用の合言葉)」と呼ばれる非常に重要な情報が必要です。
これらを故人しか知らない場合、相続人はその資産に永遠にアクセスできず、引き出すことも売却することもできなくなってしまいます。まさに「宝の持ち腐れ」です。
② 価格変動(かかくへんどう)の罠
これが最大の危険性です。暗号資産は、1日で価格が数十パーセント上下することも珍しくありません。
相続税は、原則として「亡くなった日(相続開始日)」の価格を基準に計算されます。しかし、実際に税金を納めるのは「亡くなった日から10ヶ月以内」です。
もし、亡くなった日に1億円の価値があった暗号資産が、10ヶ月後の納税時には3,000万円に大暴落していたらどうなるでしょうか? 答えは、「相続税は1億円を基準に計算された額を納めなければならない」です。手元には3,000万円しかないのに、それ以上の相続税を現金で納めるという「納税破綻(のうぜいはたん)」に陥る危険があるのです。
③ 管理・所在の不透明性
銀行口座なら通帳やキャッシュカード、証券なら取引報告書が自宅にあれば把握できます。しかし暗号資産は、どの取引所を使っているか、あるいは「ウォレット」と呼ばれる専用の機器やアプリ(例:USBメモリのような形の機器)に移しているかなど、本人以外には非常に分かりにくいのが実情です。
国内だけでなく海外の取引所も利用していたり、複数のウォレットに分散させていたりすると、相続人がその全容を把握するのは極めて困難になります。
1-3. 【事例】暴落で納税破綻? 暴騰で所得税?
暗号資産の価格変動は、相続において「暴落」と「暴騰」のどちらに転んでも深刻な問題を引き起こします。
事例(暴落):納税資金がショートするケース
被相続人Aさん(故人)の遺産:暗号資産(死亡日の評価額1億円)、預貯金500万円
相続人は長男Bさん一人。
Bさんは、相続税の申告期限(10ヶ月後)までに暗号資産を売って納税資金にしようと考えた。
しかし、市場が暴落し、暗号資産の価値は3,000万円まで下落。
【結果】相続税額は死亡日の1億円を基準に計算されるため、約2,800万円(※税率は仮)となった。Bさんの手元には、売却した3,000万円と預貯金500万円しかない。納税はできても、Bさんの手元にはほとんど現金が残らない事態となった。
事例(暴騰):思わぬ「所得税」が発生するケース
被相続人Cさん(故人)の遺産:暗号資産(死亡日の評価額3,000万円)、預貯金1,000万円
相続人は長女Dさん一人。
相続税の基礎控除(3,600万円)の範囲内だと思い、安心していた。
ところが、Dさんが遺産分割のために暗号資産を売却したところ、価格が急騰しており1億円で売れた。
【結果】相続税はかからなかったが、思わぬ落とし穴があった。Dさんは、暗号資産の値上がり益(1億円 - 3,000万円 = 7,000万円)に対して、所得税(雑所得)を納める必要が発生した。雑所得は他の給与所得などと合算され、最大で約55%(住民税含む)の税率がかかる。Dさんは翌年の確定申告で、約3,800万円(※税率は仮)もの所得税を納めることになり、慌てて税理士に相談に来られた。
このように、暗号資産の相続は「相続税」だけを考えていると、思わぬところで足をすくわれる危険性があるのです。
第2章:【国税庁指針】暗号資産の相続税評価方法を徹底解説
では、こうしたリスクのある暗号資産は、相続税を計算する上でどのように評価(いくらの価値があるとみなすか)すればよいのでしょうか。
自己流で判断するのは非常に危険です。必ず、国税庁が示しているルール(「暗号資産に関する税務上の取扱いについて(FAQ)」など)に従う必要があります。
2-1. 大原則:相続開始時(死亡日)の「時価」で評価
相続税の計算では、すべての財産を「相続開始時(=亡くなった日)」の「時価(その時点での客観的な価値)」で評価するのが大原則です。
暗号資産も例外ではありません。亡くなったその日の価格が基準となります。
2-2. ケース①:国内取引所で取引されている場合(ビットコイン、イーサリアムなど)
ビットコイン(BTC)やイーサリアム(ETH)など、私達が普段利用する暗号資産交換業者(取引所)で売買されている暗号資産については、国税庁は特別な評価方法を認めています。
これは、第1章で述べたような価格変動のリスクから納税者を守るためのルールであり、 納税者にとって最も有利な(=最も評価額が低くなる)方法を選んでよい ことになっています。
具体的には、以下の4つの価格を計算し、その中で 一番安い金額 をその暗号資産の評価額とすることができます。
- 相続開始日(死亡日)の最終価格(その日に取引された最後の価格)
- 相続開始月(死亡した月)の毎日の最終価格の平均額(例:10月20日に死亡した場合、10月1日~10月31日までの毎日の最終価格を合計し、31日で割った金額)
- 相続開始月の「前月」の毎日の最終価格の平均額(例:10月20日に死亡した場合、9月1日~9月30日までの毎日の最終価格の平均額)
- 相続開始月の「前々月」の毎日の最終価格の平均額(例:10月20日に死亡した場合、8月1日~8月31日までの毎日の最終価格の平均額)
【具体例でシミュレーション】
例えば、故人がビットコイン(BTC)を10BTC保有しており、2025年10月20日に亡くなったとします。
価格が以下だった場合、どの金額を選ぶべきでしょうか。
- 10月20日(死亡日)の最終価格:1BTC = 1,000万円
- 10月(死亡月)の月間平均価格:1BTC = 950万円
- 9月(前月)の月間平均価格:1BTC = 1,100万円
- 8月(前々月)の月間平均価格:1BTC = 900万円
この4つを比較すると、一番安いのは「8月の月間平均価格:900万円」です。
したがって、納税者はこの900万円を選び、10BTC × 900万円 = 9,000万円 を相続税の評価額として申告することができます。
もし死亡日の価格(1,000万円)しか使えなかった場合、評価額は1億円となり、相続税がより高くなってしまいます。このルールを知っているかどうかで、納税額が大きく変わる可能性があるのです。
(注意点)
- この価格は、故人が利用していた取引所の価格を使います。
- 複数の取引所を利用していた場合は、銘柄ごとに、取引所ごとに、この4つの価格を比較して最も有利なものを選びます。(非常に手間がかかります)
- 「最終価格」は、取引所が公表する「終値」や「Closing Price」などを用いますが、取引所によって定義が異なる場合があるため、税理士への確認が必要です。
2-3. ケース②:活発な市場が存在しない場合(マイナーな草コイン等)
問題は、国内の取引所では扱っていないような、知名度の低い暗号資産(通称:草コイン)の場合です。誰もが知っているような市場価格がないため、評価が非常に難しくなります。
国税庁の指針によれば、このような場合は「売買実例価額(実際に売買された価格)」や、「精通者意見価額(その暗号資産に詳しい専門家による鑑定価格)」などを参考にして評価することになっています。
しかし、現実には価格を算定すること自体が困難なケースがほとんどです。
税理士の視点から言えば、こうした暗号資産は評価方法について税務署と見解が分かれる可能性が高く、申告には細心の注意が必要です。安易に「価値ゼロ」と判断するのは危険です。
2-4. 【応用編】DeFi、NFT、ステーキング報酬の評価は?
暗号資産の技術は日々進化しており、税務上のルールが追いついていない領域も多くあります。
DeFi(デファイ:銀行などを介さない新しい金融の仕組み)
暗号資産を預けて利息を得たり、別の暗号資産と交換したりする仕組みです。ここに預けられている(ロックされている)資産も、もちろん相続財産です。その仕組み(契約内容)を一つ一つ解き明かし、死亡日時点でいくらの価値があったのか(元本+未収の利息)を評価する必要があり、極めて専門的な知識が求められます。
NFT(エヌエフティー:代わりがきかないデジタルデータ)
デジタルアートやゲームのアイテムなどです。これも財産的価値があれば相続税の対象です。しかし、NFTは一点モノが多く、客観的な「時価」がありません。評価方法は確立されていませんが、過去の取引価格、類似のNFTの取引価格、専門家の鑑定などを参考に、合理的な金額を評価額とする必要があります。
ステーキング・レンディング報酬
暗号資産を取引所やサービスに預ける(ステーキングやレンディング)ことで、利息のように報酬(暗号資産)がもらえます。死亡日までに発生していた報酬のうち、まだ受け取っていない「未収報酬」についても、財産として評価し、申告に含める必要があります。
このように、暗号資産の評価は非常に複雑です。特にDeFiやNFTが絡むと、税理士でも対応できる専門家は限られてくるのが実情です。
第3章:「バレない」は嘘!暗号資産の相続税申告漏れが発覚する理由と重い罰則

「暗号資産はデジタルデータだし、海外の取引所を使っていれば税務署にバレないのでは?」
このように考える方がいらっしゃるかもしれませんが、それは 大きな間違い です。税務署の調査能力を甘く見てはいけません。
3-1. 税務署はここまで把握している
税務署は、個人の資産状況を把握するために、強力な調査権限とシステムを持っています。
取引所(暗号資産交換業者)への調査権限
税務署は、法律に基づき、国内の暗号資産交換業者に対して「この人の取引履歴と残高をすべて開示しなさい」と命令できます。取引所はこれに応じる義務があります。相続税の調査(「税務調査」といいます)が入れば、故人や相続人の名前で開設された口座はすべて調べられると考えるべきです。
銀行口座の入出金履歴(日本円への換金履歴)
税務署は、銀行口座の履歴も徹底的に調べます。「過去に暗号資産取引所から多額の入金(=暗号資産を売って日本円にした履歴)があるのに、今回の相続税申告に暗号資産が含まれていないのはおかしい」このように、銀行口座の動きから暗号資産の保有を察知します。
CRS(共通報告基準)による国際的な情報交換
「海外の取引所なら大丈夫」という時代は終わりました。日本を含む世界100カ国以上が参加するCRSという仕組みにより、各国の税務当局が金融口座(暗号資産取引所の口座情報も含まれつつあります)の情報を自動的に交換しています。海外取引所の情報も、いずれ税務署に把握される可能性が高いです。
過去の所得税申告(雑所得)
故人が生前に暗号資産の売買で利益を出し、所得税の確定申告(雑所得)をしていた場合、税務署にはその記録が残っています。「過去に利益を出していた人が、亡くなった時に残高ゼロというのは不自然だ」と疑われるきっかけになります。
3-2. 申告漏れ・隠蔽が発覚した場合のペナルティ(罰金)
もし、意図的であれ、うっかりであれ、暗号資産の申告が漏れており、後から税務調査で指摘された場合、本来納めるべきだった相続税に加えて、重い「追徴課税(ペナルティ)」が課されます。
- 延滞税(えんたいぜい)
納付期限(死亡から10ヶ月)に遅れたことに対する利息です。時間が経つほど増えていきます。 - 過少申告加算税(かしょうしんこくかさんぜい)
「申告したけど、金額が少なかった」という場合に課されます。追加で納める税金の10%~15%が上乗せされます。 - 無申告加算税(むしんこくかさんぜい)
「そもそも相続税の申告自体をしていなかった」という場合に課されます。追加で納める税金の15%~20%が上乗せされます。 - 重加算税(じゅうかさんぜい)
これが最も重いペナルティです。「意図的に財産を隠した(隠蔽・仮装)」と判断された場合に課されます。追加で納める税金の35%~40%が上乗せされます。
暗号資産の存在を知っていたのに意図的に申告しなかった場合、この「重加算税」の対象となる可能性が非常に高いです。
3-3. 【税理士が見た】申告漏れしやすい危険なケースワースト3
税務の現場で、実際に申告漏れにつながりやすい危険なケースをご紹介します。
第1位:家族に内緒で個人ウォレットに保管
取引所ではなく、USBメモリのような専用機器(ハードウェアウォレット)や、スマホのアプリ(ソフトウェアウォレット)に暗号資産を移しているケースです。これらは故人しか存在を知らず、家族がその機器やアプリを見つけられない、あるいは見つけても「復元用の合言葉(リカバリーフレーズ)」が分からず、申告から漏れてしまいます。
第2位:複数の海外取引所に分散
国内の取引所は把握していたが、故人が海外の取引所も利用していたことに相続人が気づかないケース。特にメールアドレスなども共有されていないと、把握は困難です。
第3位:「暴落して価値が減ったから申告不要」という自己判断
「どうせ暴落して価値がほとんどないから」と、相続人が自己判断で申告に含めないケース。しかし、第2章で解説した通り、評価はあくまで「死亡日」が基準です。死亡日に一定の価値があれば、たとえその後ゼロになったとしても申告は必要です。
第4章:【生前対策】今すぐやるべき「暴騰・暴落」と「アクセス不能」への備え
ここまで暗号資産の相続の危険性をお伝えしてきましたが、これらのリスクは「生前対策」によって大きく軽減することができます。暗号資産を保有している方は、ご自身とご家族のために、今すぐ以下の対策を実行してください。
4-1. 最大のリスク「アクセス不能」を防ぐ「デジタル遺産」の整理
相続人が資産にたどり着けなければ、評価も納税もありません。まずは「存在」と「アクセス方法」を確実に伝える準備が最重要です。
エンディングノート(遺言書とは別)に何を記すべきか?
万が一の時に家族が見るノートに、以下の情報を整理して残しましょう。
OK(残すべき情報):
- 利用している「取引所名」(bitFlyer、Coincheck、海外のBinanceなど)
- 利用している「ウォレットの種類」(例:レジャーナノ(Ledger Nano)というUSB機器、メタマスク(MetaMask)というアプリ、など)
- 保管場所(例:USB機器は書斎の金庫の中、など)
- どのメールアドレスで登録しているか
NG(危険な情報):
- 取引所の「パスワード」そのもの
- ウォレットの「秘密鍵」や「リカバリーフレーズ(合言葉)」そのもの
なぜパスワード等を直接書いてはいけないかと言うと、そのエンディングノートが盗まれたり、他人に見られたりした場合、全財産が盗まれてしまうからです。
安全な「重要情報」の残し方(税理士推奨)
では、肝心のパスワードや合言葉はどう残すべきか。
- 「リカバリーフレーズ(合言葉)」は必ず 紙に 書き出します。(PCやスマホ、クラウド上での保存はハッキングの危険があり非推奨)
- その紙を、エンディングノートとは 別の場所 に厳重に保管します。(例:貸金庫、耐火金庫など)
- エンディングノートには「合言葉を書いた紙は、〇〇銀行の貸金庫に預けてある」という 保管場所の情報だけ を記します。
こうすることで、ノートを見られても直接資産を盗まれず、家族だけが重要情報にたどり着けるようになります。
二段階認証の壁
取引所へのログインには、ID・パスワードの他に「二段階認証」(スマホの認証アプリに表示される6桁の数字など)が必要な場合がほとんどです。故人のスマホがロックされていて認証アプリを開けない、という問題が多発しています。スマホのロック解除方法も、エンディングノートに必ず記載してください。
4-2. 保有状況の「一覧化」と「取引履歴」の保存
ご自身でも、今どこに何を持っているか正確に把握できていない方が意外と多いです。
Excelやスプレッドシートなどで、以下のような「暗号資産管理一覧表」を作成し、定期的に更新しましょう。
| 銘柄名 | 保有数量 | 保管場所(取引所名/ウォレット名) | 取得日(いつ買ったか) | 取得価額(いくらで買ったか) |
|---|---|---|---|---|
| BTC | 1.5 | A取引所 | 2020/5/10 | “1,500,000円” |
| ETH | 20 | B取引所 | 2021/1/15 | “2,000,000円” |
| XYZ | 10000 | 個人ウォレット (Ledger) | 2022/3/1 | “100,000円” |
この「取得価額」の情報は、相続人が将来その暗号資産を売却する際に、所得税の計算で必ず必要になるため非常に重要です。
また、各取引所から「年間取引報告書」や「取引履歴(CSVデータ)」を少なくとも年に1回はダウンロードし、PCやUSBメモリに保存しておくことを強く推奨します。(取引所が閉鎖したり、過去のデータがダウンロードできなくなったりするリスクに備えるためです)
4-3. 納税資金対策①:生前贈与の活用
相続税は、原則として「現金一括払い」です。暗号資産のまま納めることはできません。
相続財産が暗号資産ばかりだと、相続人が納税資金に困ることは明らかです。
対策として、元気なうちに「生前贈与」で家族に資産を移しておく方法があります。
暦年贈与(れきねんぞうよ): 1人あたり年間110万円までの贈与であれば、贈与税がかかりません。
暗号資産を贈与する場合も、贈与した日の「時価」で評価します。110万円の枠内で少しずつ贈与することが可能です。
注意点: 贈与した証拠を残すため、「いつ、誰に、何を、どれだけ贈与したか」を記した「贈与契約書」を必ず作成してください。
4-4. 納税資金対策②:計画的な「利確(現金化)」
ご自身の資産の配分(アセットアロケーション)を見直し、暗号資産の比率が極端に高くなっている場合は、暴落リスクに備えて、一部を売却(利確)して現金化しておくことも重要です。
特に、市場が過熱して価格が暴騰しているタイミングは、納税資金を確保する良い機会かもしれません。
注意点: 暗号資産を売却して利益が出た場合、その利益は「雑所得」として、翌年に所得税の確定申告が必要です。売却した年の給与所得などと合算され、最大で約55%(住民税含む)の税金がかかります。「税金を払ってでも現金を確保する」という判断が必要です。
4-5. 納税資金対策③:生命保険の活用
相続税の納税資金対策として、最も有効な手段の一つが「生命保険」です。
ご自身を被保険者(保険をかけられる人)、相続人(妻や子)を保険金の受取人とする死亡保険に加入します。
メリット:
- 死亡後、すぐに現金が受取人(相続人)に振り込まれるため、納税資金に確実に充てられます。
- 死亡保険金には「500万円 × 法定相続人の数」という強力な非課税枠があります。
- 例えば、法定相続人が妻と子供2人(計3人)の場合、500万円 × 3人 = 1,500万円 までは、死亡保険金を受け取っても相続税がかかりません。預貯金で1,500万円残すよりも、税制上はるかに有利です。
第5章:【相続発生後】暴落しても慌てない!死後10ヶ月の必須手続き

もし、ご家族が亡くなり、暗号資産の相続が発生してしまったら。
相続税の申告・納税期限は「死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内」です。時間は限られています。慌てずに、以下のステップで進めてください。
5-1. ステップ1:資産の全容把握(相続開始~3ヶ月)
まずは、故人がどこにどれだけの暗号資産を持っていたかを特定します。
- エンディングノート、遺言書がないか探す。
- 故人のPC(ブックマーク、ファイル)、スマホ(取引所のアプリ)、メール(取引所からの通知)を徹底的に確認する。
- 故人の銀行口座の入出金履歴を取り寄せ、取引所との入出金がないか確認する。
- 書斎や金庫、貸金庫などに、USBメモリのような機器(ハードウェアウォレット)や、合言葉を記した紙片がないか探す。
- 取引所が特定できたら、すぐに電話やメールで「口座名義人が死亡した」旨を連絡し、死亡日時点の「残高証明書」や「取引履歴」の発行を依頼します。
5-2. ステップ2:遺産分割協議
相続人が複数いる場合、見つかった暗号資産を含むすべての遺産を「誰が」「どう分けるか」を話し合う「遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)」を行います。
暗号資産の分け方は主に3つあります。
- 現物分割(げんぶつぶんかつ)
「長男がビットコイン、長女がイーサリアム」のように、暗号資産のまま分ける方法。 - 換価分割(かんかぶんかつ)
相続人の代表者が、一旦すべての暗号資産を売却(日本円に換金)し、その現金を相続人間で分ける方法。最も公平でトラブルが少ない方法です。 - 代償分割(だいしょうぶんかつ)
相続人の一人がすべての暗号資産を取得する代わりに、他の相続人に対して自分の現金(代償金)を支払う方法。
【要注意!】換価分割の「所得税」問題
ここで、第1章の事例でも触れた「所得税」の問題が再浮上します。
相続人が暗ho資産を売却(換価分割)した際、もし「死亡日の評価額」よりも「売却時の価格」が値上がりしていた場合、その値上がり益には相続人の所得税(譲渡所得)がかかります。
(例)死亡日に3,000万円だった暗号資産を、相続人が売却したら3,500万円になった。→ 値上がり益500万円に対して、相続人が所得税を納める義務がある。
この税金は相続税とは「別」にかかるものです。これを知らずに売却代金をすべて分けてしまうと、後で代表して売却した相続人のもとに多額の納税通知が届き、トラブルになるケースがあります。
5-3. ステップ3:相続税評価額の確定と申告(~10ヶ月)
ステップ1で集めた資料(残高証明書、取引履歴)をもとに、第2章で解説した「4つの評価方法」を適用し、相続税の評価額を確定させます。
銘柄ごと、取引所ごとに、4つの価格(死亡日、当月平均、前月平均、前々月平均)をすべて計算し、最も安い価格を選びます。
市場が暴落している局面では、死亡日の価格ではなく「月次平均価額」を使った方が圧倒的に有利(評価額が低く)になるケースが多いです。
すべての財産(預貯金、不動産、暗号資産など)の評価額を合計し、相続税申告書を作成します。
この評価額の算定は非常に手間がかかり、専門知識も要するため、暗号資産がある場合は必ず税理士に依頼してください。
5-4. ステップ4:納税
申告書を税務署に提出し、計算された相続税額を、死亡から10ヶ月以内に金融機関などで納付します。
納税は必ず「現金一括払い」が原則です。暗号資産のまま納めることはできません。
もし、価格暴落などでどうしても現金が用意できない場合は、「延納(分割払い)」や「物納(不動産などで納める)」といった制度もありますが、条件が厳しく、暗号資産そのものは物納の対象にはなりません。やはり、生前からの納税資金対策が最も重要です。
第6章:暗号資産の相続に関するQ&A
Q1. 故人がどの取引所を使っていたか全く分かりません。調べる方法は?
A. まずは故人の銀行口座の入出金履歴(通帳やネットバンキング)を確認してください。取引所への入金(振込)や、取引所からの出金(振込)があれば、その振込名義人から利用していた取引所が判明するケースがほとんどです。
また、スマホのアプリ一覧、PCのブックマーク、Eメールの受信箱(「~取引所からのお知らせ」など)も徹底的に調査してください。
Q2. 秘密鍵を紛失し、アクセス不能な暗ho資産も相続財産になりますか?
A. 非常に難しい問題です。税務上の原則論で言えば、取引所の残高証明書などで「存在が確認できる」以上、たとえアクセス不能(事実上、引き出せない)であっても、死亡日の時価で評価し、相続財産として申告する必要があります。
ただし、相続人がアクセスできないことを客観的に証明(取引所からの回答書など)した上で、その財産的価値が著しく低いものとして評価減を主張できる可能性はゼロではありません。これは高度な税務判断となるため、必ず税理士にご相談ください。
Q3. 相続した暗号資産を売却しました。経費にできる「取得費(買った値段)」はいくらになりますか?
A. 相続人が売却する際の取得費は、「被相続人(故人)が、その暗号資産をいくらで買ったか」という、故人の取得価額を引き継ぎます。
多くの方が「相続税の申告で使った評価額(死亡日の時価)」が取得費になると勘違いされていますが、違います。
故人がいつ・いくらで買ったかが分からないと、最悪の場合、売却額の5%しか取得費として認められず、多額の所得税がかかる危険があります。だからこそ、生前の「取引履歴の保存(第4章)」が重要なのです。
Q4. 相続税の「取得費加算の特例」は暗号資産にも使えますか?
A. 使えません。(2025年10月現在)
「取得費加算の特例」とは、相続税を納めた人が、相続した財産(土地や株など)を一定期間内に売却した場合、納めた相続税の一部を売却時の取得費に上乗せして、所得税を安くできる制度です。
残念ながら、暗号資産はこの特例の対象資産に含まれていません。
第7章:まとめ:暗号資産の相続は「生前対策」と「専門家」が鍵
本記事では、暗号資産(仮想通貨)の相続税評価と、申告漏れのリスクについて詳しく解説してきました。
- 暗号資産は価格変動が激しく、「死亡日の評価額」と「納税時の価格」が大きく乖離(かいり)し、納税破綻を招くリスクがあります。
- 評価方法は国税庁の指針(4つの価格から有利なものを選択)に従う必要がありますが、DeFiやNFTが絡むと非常に複雑になります。
- 「バレないだろう」という申告漏れは、税務署の調査でほぼ発覚し、重いペナルティ(重加算税など)が課されます。
- 最大のリスクである「アクセス不能」を防ぐため、保有者(被相続人)は、生前に「資産の見える化(一覧表)」と「アクセス情報(合言葉の保管場所など)の共有」を必ず行うべきです。
- 相続が発生したら、自己判断せず、速やかに専門家に相談することが不可欠です。
最後にお伝えしたいのは、暗号資産の相続は、税理士なら誰でも対応できるわけではない、という現実です。
相続税の知識はもちろんのこと、「暗号資産の税務(所得税計算)」や「ブロックチェーンの技術的な仕組み」にも精通した、経験豊富な専門家を選ぶことが極めて重要です。
ご自身、そしてご家族が、暗号資産の相続で「こんなはずではなかった」と後悔しないために。
まずはご自身(またはご家族)の保有状況の確認から始めてみてください。そして、少しでも不安があれば、暗号資産に強い税理士へ相談することをお勧めします。
【免責事項】
本記事は、2025年10月24日現在の日本国の税法、関連法令および国税庁の公表資料等に基づき作成しています。
税法やその解釈は将来的に変更される可能性があります。
本記事は、暗号資産の相続に関する一般的な情報提供を目的としており、特定の個人に対する個別具体的な税務アドバイスを行うものではありません。
暗号資産の評価、申告、納税、または生前対策の実行にあたっては、必ず税理士等の専門家にご相談いただき、ご自身の責任においてご判断ください。
本記事の情報に基づいて被ったいかなる損害についても、監修者および運営者は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。